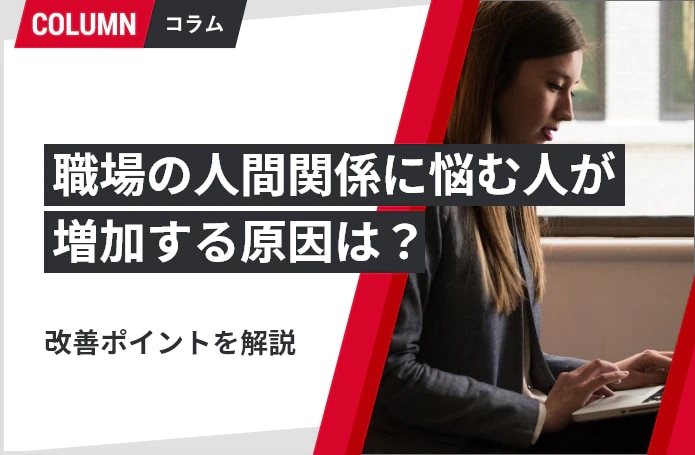
職場の人間関係に悩む人が増加する原因は?改善ポイントを解説
職場における上司や同僚、部下との「人間関係」は、仕事へのモチベーションに大きな影響を与える重要なファクターです。職場の人間関係で悩みを抱えていると仕事に支障が生じるだけでなく、心身の不調にもつながるおそれがあります。
今回は、職場の人間関係のストレスからくる症状や、人間関係の悩みを改善する方法などについて解説していきます。
目次[非表示]
職場の人間関係に悩む人はどのくらいいる?
日本労働調査組合が全国20~49歳の会社員を対象におこなった調査では、職場の人間関係について何らかの悩みやストレスがあると回答した人が約3割いたことが分かりました。
年代別では、「職場の人間関係が良好である」と答えたのは20代がもっとも多く、30代、40代と年齢が上がるにつれ「良好」だと答える人は少なくなりました。
「職場の人間関係にストレスを感じている」と答えた年代は40代がもっとも多く、20代がもっとも少ないという結果に。年齢の高い従業員ほど、人間関係に問題を感じている傾向が見られました。
さらに、58.5%の人が「職場の人間関係を理由に退職・転職を考えたことがある」と回答しています。従業員の離職率低減を図る企業にとって、職場の人間関係づくりは非常に重要なテーマであると言えるでしょう。
※参考:【日労公式】職場の人間関係を良好と感じているのは全体で約3割|日本労働調査組合
職場の人間関係の悩み・ストレスからくる症状
職場の人間関係に悩みを抱えた状態が続くと、ストレスから心身に異常が生じるおそれがあります。ストレスからくる症状は一般的に、精神的な症状、肉体的な症状、行動的な症状に分類されます。
▼ストレスマネジメント関する記事はこちら
ストレスマネジメントとは?対処方法や効果を解説
■精神的な症状
職場の人間関係によるストレスが溜まると、メンタルに異常をきたすケースが少なくありません。以下のような症状が見られる場合は注意が必要です。
- 気分が落ち込みがちで憂うつ
- 注意力、集中力、気力、思考力、決断力が低下する
- 新しい物事に対する意欲が減少する
など
ストレスによってメンタル面に負担がかかっているときは、これらの症状以外にも様々なサインがあらわれます。
■うつ病・適応障害
職場の人間関係からくるストレスが長期化すると、うつ病や適応障害に陥るリスクがあります。うつ病や適応障害に陥ると、抑うつ状態、不安、怒り、焦り、緊張などの症状があらわれます。
そうなると、仕事上の影響は避けられず、通常の業務をこなせなくなってしまいます。治療も長期間を要する傾向にあるため、休職や退職に追い込まれてしまうケースもあります。
■HSP
HSPとは「Highly Sensitive Person」の略で、神経が細やかで感受性が強い性質の人のことを言います。アメリカの心理学者であるエレイン・アーロン博士が提唱した概念で、日本語では「敏感すぎる人」と訳されることもあります。
HSPは繊細な神経を持っており、他の人よりも感情や刺激に敏感です。職場における刺激に対しても過剰な反応を示すことがあり、それがストレスや不安につながることも少なくありません。また、HSPは職場での人間関係においても周囲の人の感情や態度に影響を受けやすく、他の人のマイナスなエネルギーやストレスが彼らに波及することも多々あります。このようにHSPはその感受性や繊細さによりストレスや不安を抱えやすく、職場の人間関係で苦労したり悩みを抱えやすくなったりする傾向があります。
■肉体的な症状
人間関係によるストレスは肉体にも影響を及ぼします。個人差はありますが、以下のような症状があらわれる可能性があります。
- 疲れやすい、倦怠感
- 肩こり、頭の痛み
- 目の疲れ・目まい
- 食欲不振、動悸・息切れ
- 睡眠障害
など
これらの症状の原因は必ずしもストレスばかりではなく、特定の疾病が原因になっている可能性もあります。症状が深刻な場合は、早めに医師の診察を受けるようにしましょう。
■行動的な症状
過大なストレスによって、日々の行動に変化があらわれるケースも多々あります。よくある行動の変化としては、以下のようなものが挙げられます。
- 仕事上のミスが増える
- 遅刻・早退や欠勤が増える
- 周囲とのコミュニケーションが減少する
- 身だしなみが乱れる
など
このような症状を放置していると、後述するうつ病や適応障害に発展するケースもあるため、できるだけ早めの対策が肝心です。
職場の人間関係がうまくいかない原因
職場の人間関係でストレスを溜めないようにするためには、前提として「人間関係がうまくいかない原因」を知っておくことが大切です。職場の人間関係がうまくいかない原因として考えられるのは以下の3点です。
■上下の人間関係:業務難易度の見立てがすり合わない
人間関係がうまくいかない原因として、上司と部下間で業務難易度の見立てがすり合わないということが考えられます。
例えば、上司が「この人にならできる!」と思っている難易度だったとしても、部下が「できない」と思ってしまっているときに部下に干渉せず任せてしまうと、仕事は進まず、部下は「なぜ何も教えてくれないんだ」と不満を持つきっかけになります。
また、上司は「できない」と思っていても、部下が「できる」と思っているときに、具体的な進め方を丁寧に教えてしまうと、部下は「信頼されていないんだ」と感じてしまい、不信感を持つ可能性があります。
お互いに対してネガティブな感情がなかったとしても、物事に対する捉え方が異なっているため、意図していない意味で言葉が伝わってしまい、うまく関係構築できないということが起こり得ます。
■横の人間関係:組織の多数がTakeの思考になっている
アメリカの組織心理学者であるアダム・グラントは、『GIVE&TAKE 「与える人」こそ成功する時代』(三笠書房、2014年)という本の中で、ギブ&テイクの関係の中で、自分が受け取る以上に他人に与える「ギバー」、常に、与えるより多くを受け取ろうとし、自分の利益を優先する「テイカー」、ギブとテイクのバランスを取ろうとする「マッチャー」の3種類がいると記しています。
ビジネスにおいては、マッチャーになる人が多いですが、もし同僚との人間関係がうまくいっていないと感じるのであれば、無自覚のうちにお互いがテイカー的な思考になっており、他者からの利益を求めすぎている可能性があります。
また、逆に自分がギバーになりすぎており、必要以上の負担を背負いすぎている可能性もあります。
どちらにせよ、ギブ&テイクのバランスがとれていなければ、利益・不利益に偏りが生じ、人間関係がぎくしゃくする可能性があります。
■人間関係全般:日々のコミュニケーションが不足し、お互いの状況や感情を知らない
先述した、業務難易度の認識齟齬やギブ&テイクの思考特性の他にも、仕事量やアサインメント、自身の成長角度や評価など、自分の認識と周囲にいる上司や同僚の認識がすり合わないものはたくさん発生します。
それは、個人個人の生まれや育ち、過ごしてきた時間が違う以上、事象に対する捉え方や感じ方は個人個人で異なっており、視界の個別性があるからです。
ある人物の発言や判断が、自分の思っている判断と異なるとき、人は不満や不平を感じることがあります。
それは、その発言や判断の背景にどのような理由があるのか、どのような感情やどのような事情があるのかは、自分の感じている理由や感情、事情と大きく異なっているにも関わらず、理解していないためです。
日々のコミュニケーションが不足していると、発言や判断の背景にある理由や感情、事情を理解する機会がないため、悪気なくネガティブな感情を抱いてしまうことが多くなります。
▼辞める人に関する記事はこちら
本当に辞める人の特徴は何も言わないこと?兆候や理由について解説
職場の人間関係が良好な場合のメリット
人間関係が良好な職場のメリットとしては、従業員が高いモチベーションで楽しく働けることや生産性の向上につながること、離職率の低下につながることなどが挙げられます
メリット①従業員が高いモチベーションで楽しく働ける
良好な人間関係が築かれている職場では、楽しさややりがいが醸成されやすく、従業員のエネルギーやモチベーションが引き出されます。また、オープンなコミュニケーションがおこなわれているため、組織内で誤解や摩擦が生じにくくなります。従業員はストレスを抱えることが少なく、心身の健康を維持しながら楽しく意欲的に働くことができるでしょう。
メリット②生産性の向上につながる
良好な人間関係が築かれている職場は、総じてチームワークが良い傾向にあります。従業員同士に信頼関係ができていて、お互いをサポートし合いながら仕事に取り組んでいるため、生産性も向上しやすくなります。また、従業員が自由に意見やアイデアを共有できるので創造的な解決策やイノベーションが生まれやすく、生産性にプラスの影響をもたらすこともあります。
メリット③離職率の低下につながる
常に離職理由の上位に挙がるのが「職場の人間関係」ですが、良好な人間関係が築かれている職場では、従業員が人間関係で悩むことがありません。多くの従業員が働きやすさや居心地の良さを感じており、満足度やエンゲージメントが高い状態にあるため、その職場において長期的なキャリアの展望を持つことができます。結果的に、従業員の定着率が高まり、離職率の低下につながります。
職場の人間関係の悩みを解消する方法
職場において人間関係の悩みを抱え続けている状態は、従業員にとっても会社にとってもリスクの高い状態です。
仕事のパフォーマンス低下や離職につながる可能性があるので、できるだけ早く悩みを解消するための対策を講じるべきです。職場における人間関係の悩みを解消する方法をいくつかご紹介します。
■背景・理由をすり合わせる
仕事を進める中で、気になった判断や発言に対してはその背景にある意図や理由を都度すり合わせるようにしましょう。前述した通り、個人個人が過ごしてきた時間や経験が違うからこそ、視界の個別性は絶対に発生します。
そのため、自分は納得できない、違和感を持つ発言や判断が発生することは当たり前で、避けられないことでもあります。
ただ、相手も誰かを攻撃したくてそのような発言・判断をしているわけではないことが大半です。最初は違和感があった判断や発言も、その背景にある理由や感情を聞けば、思いのほか納得できることも多くあります。
また、すり合わせの過程で自分が他者に求めすぎているテイカー思考に気付いたり、逆に自分が周囲に対して与えすぎているギバーになっていることに気付いたりすることもできるので、双方にとって良い関係性を見出すきっかけになります。
このように、すり合わせをすることで相手の判断基準を理解し、自身の状況も伝えることができれば、ネガティブな感情を抱くことも少なくなり、結果として人間関係の悩みが解消されることに繋がります。
■休息・リラックスできる時間を増やす
誰にでもストレスはあるものですが、あまりにも過剰なストレスが溜まってしまうと自分で精いっぱいになってしまうので、他者と背景や理由をすり合わせる余裕もなくなってしまいます。
ストレスをゼロにすることはできませんが、ストレスを溜めすぎないように工夫することが大切です。そのためには、日々適度な休息をとったり、リラックスできる時間を設けたりすることが大切です。
特に、重要だと言われるのが睡眠です。睡眠は体だけでなく脳も休ませてくれるため、心身ともにリフレッシュすることができます。睡眠不足が続くとストレスを解消できないので、朝すっきり目覚めることができる程度の睡眠時間を心がけましょう。
■働き方を変える
職場における人間関係の悩みを解消する方法として、働き方を変えてみることもおすすめです。働き方改革の一環としてフレックスタイムや時短勤務を導入する会社も増えていますし、コロナ禍をきっかけにリモートワーク・在宅勤務や時差出勤なども一般的になりました。
働き方を変えること自体が気分転換になりますし、自分の時間を持ちやすくなるためストレス解消にもつながります。極端な話、リモートワークにすれば職場の苦手な人と顔を合わせる機会も少なくなります。
また、上記の方法を試しても全く状況が改善されない場合は、思い切って転職してしまうという手段もあります。ただ、どの職場でもすり合わせが行われなければいつまでも周囲が理解できず、苦しいままになってしまうので、転職後も周囲の人との対話やすり合わせは行うようにしましょう。
■サポートする仕組みを作る
メンターを置くことは、職場の人間関係を改善するための効果的な手段の一つです。メンターが従業員の精神的なサポートすることで、職場の人間関係が円滑になるケースも少なくありません。
メンターに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
>> メンターとは?メンターの意味や役割、制度のポイントを解説
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0105
また、職場の風通しを良くして、組織全体で協力姿勢が生まれる風土を醸成することも人間関係の改善につながります。風通しの良い職場のメリットなどは、以下の記事で詳しく解説しています。
>> 風通しの良い職場とは?メリット・デメリットや具体的な施策案をご紹介
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0009
まとめ
人間関係が良い職場では、従業員も高いモチベーションで働くことができます。その結果、仕事のパフォーマンスも上がりますし、従業員の定着率も高まります。人間関係が悪い職場はその逆で、仕事の生産性が低下し、従業員の離職率も高まります。
職場の人間関係を良くする特効薬はありませんが、職場環境やコミュニケーションを見直しながら、地道に良い人間関係を作っていきましょう。
【ケース別】職場の人間関係解消法
職場の人間関係に悩む人が抱えている問題は様々です。職場の人間関係を改善するためのヒントをケース別にご紹介していきましょう。
ケース①相手に嫌われたくない
「相手に嫌われたくない」という気持ちが強いあまり、職場の人間関係の悩みが深くなってしまうケースがあります。このようなケースで重要なことは、自分自身を偽らずに自然体でいることです。相手に気に入られるために自分を変える必要はありません。自分の価値観や個性を大切にし、ありのままの自分を表現することが良好な人間関係の基礎になります。また、自分に対してネガティブな評価をせず、自己肯定感を高めることも重要です。自分の価値を認め、自信を持つことで、他人の意見や批判に対して強くなることができます。
ケース②相手が嫌い
単純に「相手が嫌い」なことが、職場の人間関係が悪化する原因になることも少なくありません。このような場合、嫌いな人との関わりを最小限に抑えることも一つの方法です。業務上の関わりは避けられないかもしれませんが、できるだけ個人的な話題での交流は避けるようにしましょう。嫌いな人と距離をとることで、ストレスや不快感を減らすことができます。関わりを避けられない場合は、ビジネスだと割り切って淡々とした態度で接するようにしてください。感情は抑え、一歩引いて冷静に対応するように心がけましょう。
ケース③相手が変わってくれない
「相手が変わってくれない」という不満から、職場の人間関係に悩んでいる人も多いでしょう。相手が変わるのを期待することは、自分のがっかり感やストレスを増大させることにつながります。このような場合は、相手に変わってほしいと期待するよりも、現実を受け入れることにフォーカスしたほうが良いでしょう。他人を変えることは難しいですが、自分自身の対応や反応を変えることは可能です。他人に依存することなく、自分が主体となって仕事のやりがいや成長を追求していきましょう。
ケース④相手に嫉妬してしまう
「相手に嫉妬してしまう」ことが、職場での人間関係に悪影響を与えることがあります。このような場合は、自分自身の価値や成果を認めるように努めましょう。こうして自己肯定感を高めることができれば、他人と比較することに固執しなくなり、嫉妬の感情も和らぐでしょう。また、目標を持ってスキル・能力の向上に努めることも重要です。新しいスキルや知識を身に付けることで、他人のことを気にするよりも自己成長に喜びを見いだせるようになるでしょう。
ケース⑤相手に心を許せない
「相手に心を許せない」ことによって、職場での人間関係をこじらせてしまうこともあります。相手に心を許すためには、自分自身が率先して自己開示を試みることが重要です。ふとしたコミュニケーションの場で少しずつ自分について話したり感情を共有したりすることで、相手もオープンな態度になってくれるものです。また、相手と共通の利益や目標を見つけることも重要です。共通の目的・目標に向かって協力することで信頼関係が築かれ、心を許しやすくなっていくでしょう。
よくある質問
職場の人間関係に悩む人はどのくらいいる?
日本労働調査組合が全国20~49歳の会社員を対象におこなった調査では、職場の人間関係について何らかの悩みやストレスがあると回答した人が約3割いたことが分かりました。
さらに、58.5%の人が「職場の人間関係を理由に退職・転職を考えたことがある」と回答しています。従業員の離職率低減を図る企業にとって、職場の人間関係づくりは非常に重要なテーマであると言えるでしょう。
職場の人間関係の悩み・ストレスからくる症状は?
職場の人間関係の悩み・ストレスからくる症状として以下のようなものがあります。
■精神的な症状
■うつ病・適応障害
■肉体的な症状
■行動的な症状
職場の人間関係がうまくいかない原因は?
職場の人間関係がうまくいかない原因として考えられるのは以下の3点です。
■上下の人間関係:業務難易度の見立てがすり合わない お互いに対してネガティブな感情がなかったとしても、物事に対する捉え方が異なっているため、意図していない意味で言葉が伝わってしまい、うまく関係構築できないということが起こり得ます。
■横の人間関係:組織の多数がTakeの思考になっている ビジネスにおいては、マッチャーになる人が多いですが、もし同僚との人間関係がうまくいっていないと感じるのであれば、無自覚のうちにお互いがテイカー的な思考になっており、他者からの利益を求めすぎている可能性があります。
■人間関係全般:日々のコミュニケーションが不足し、お互いの状況や感情を知らない 先述した、業務難易度の認識齟齬やギブ&テイクの思考特性の他にも、仕事量やアサインメント、自身の成長角度や評価など、自分の認識と周囲にいる上司や同僚の認識がすり合わないものはたくさん発生します。






