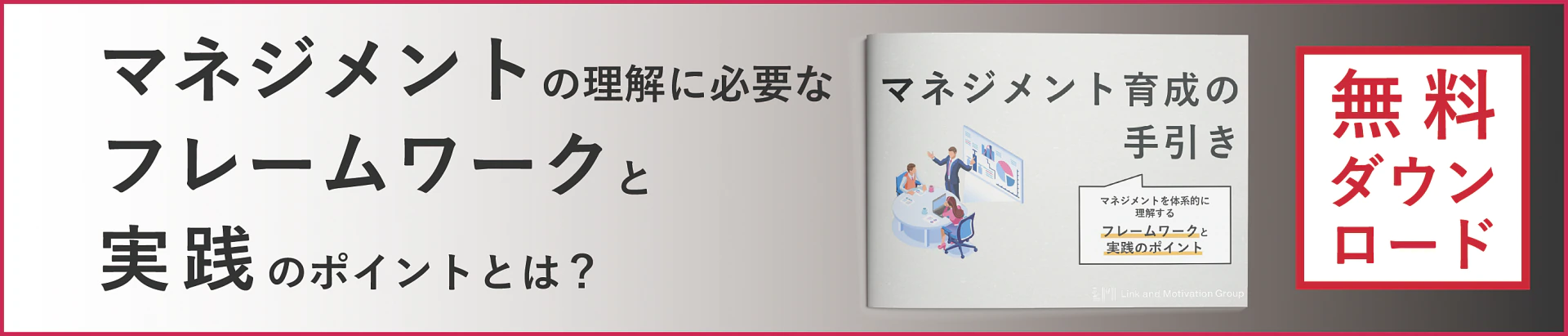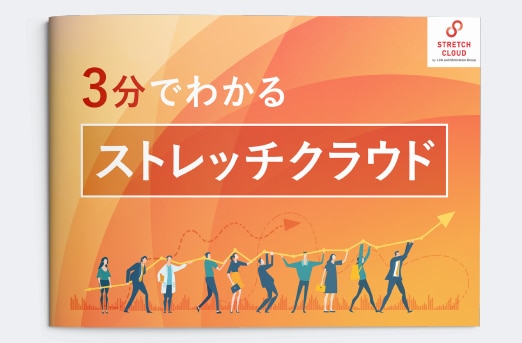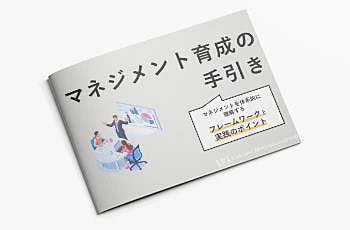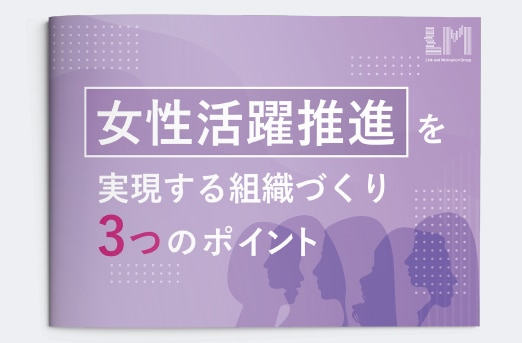年5回の研修を軸にした伴走型の育成プログラムで、マネジャーの「ピープルマネジメント力」向上を
実現
パイオニア株式会社

|
事業内容 業種 |
カーエレクトロニクス分野を中心とした製品・サービスの展開 機械・エレクトロニクス |
|---|---|
| 企業規模 |
7,655名(連結ベース:2024年3月末) |
| 担当コンサルタント | 齋藤章成 |
| 導入サービス |
モチベーションクラウド ロールディベロップメント(旧ストレッチクラウド) |
課題
-
事業変革を実現するために、エンジニアにもマネジャーにも求められるスキルが多様化・高度化していた。
-
従来から、業務管理が得意なマネジャーは多かったが、それだけでなくメンバーの力を引き出すピープルマネジメント力の向上が求められていた。
効果
-
アドバイススクランブル(サーベイ結果を基に参加者同士でアドバイスし合う、研修内のプログラム)では、実際の業務に即した質問ができ、具体的なアドバイスをもらえるため、より実践的な学びを得ることができた。
-
マネジャーの意識・行動の変化をポジティブに受け止める上司・部下が増えてきた。
-
直近のマネジメントサーベイの定量結果も、改善傾向にある。
確かな「モノづくり力」を礎に、“モノ”דコト”で新しい価値を提供
「事業内容および部署の概要」
福井氏:パイオニアは、スピーカーの製造・販売を祖業とする会社です。近年はカーエレクトロニクスに注力しており、主にスピーカーやカーナビ、ドラレコ、直近ではナビゲーション用のスマホアプリなどを開発しています。
当社はもともと組み込みプロダクトに強みを持っていましたが、近年は「モノとコトの融合」という大きな変革に舵を切っており、クラウド技術を活用したコト(サービス)もつくっていく必要があります。
そこで、クラウド技術に関する知見・ノウハウを備えた人材を育てていくために、私が所属する「リスキリング推進室」が発足しました。現在、リスキリング推進室はクラウドエンジニアの育成とクラウドサービス開発・運用部門の組織開発に注力しています。
マネジャーに求められていた「ピープルマネジメント力」
「サービス導入前の課題」
福井氏:今申し上げたように、「いかにモノとコトを融合させていくか」が当社の課題でした。新たにクラウド領域に挑戦する必要があり、エンジニアにはより多様で高度なスキルが求められるようになりました。これはマネジャーも同様で、今までどおりのスキルでは通用しないことは明らかでした。
当社のマネジャーのほとんどはモノづくりの領域で成果を出してきた人たちだったので、「モノとコトの融合」という壁に直面し、悩んでいたと思います。事業の方向性を変えるのであれば、スキルや組織運営の方法も変えていかなければいけません。しかし、そのやり方が分からない状態でした。
当社のマネジャーは業務管理は得意だと思います。しかし、メンバーの力を引き出すピープルマネジメントは今まで注力してこなかった領域でもあるので、伸びしろがあると感じていました。マネジャーは、「期限までにプロダクトをつくりなさい」と言われるのと同時に、「メンバーも育てなさい」と言われます。「そんな時間はない」というのが正直なところだったと思います。最初は、モノづくりと人材育成は両立できないと考えているマネジャーもいました。
ですが、組織としても事業としても成長を遂げるためには、業務管理だけではなく人材育成も必要です。そこで、CTOから「ピープルマネジメントに力を入れていこう」と号令がかかり、リスキリング推進室が動き出しました。

マネジャーの成長を支援し続ける「伴走型」のサービスを求めていた
「リンクアンドモチベーションを選んだ決め手」
福井氏:マネジャーの育成、特にピープルマネジメント力の向上を図るために様々なサービスを探しているなかで、リンクアンドモチベーションのモチベーションクラウド ロールディベロップメント(旧ストレッチクラウド)を知りました。サービスを選定するうえで私の根底にあったのは、「今日取り組んで、明日すぐに変わることはない」ということです。人材育成は地道な取り組みであり、長い目で効果を見ていかなければいけません。ですから、一度研修を受けて終わりではなく、半年後、1年後と、マネジャーの成長をモニタリングしていけるような伴走型のサービスを探していました。
研修を受ければ、そのときだけは意識が変わるかもしれません。ですが、人間はすぐに忘れてしまいます。次の日には半分忘れ、3日もすれば2割くらいしか覚えていないでしょう。これでは行動は変わっていきません。行動が変わらなければ、何もしなかったのと同じです。もちろん、早くに変化が現れるに越したことはありませんが、最低でも半年から1年くらいはフォローし続けていくべきだというのが私の考えでした。
そんな中、縁がありリンクアンドモチベーションからご提案をいただきましたが、その内容が2年間の育成プログラムでした。2年かけてマネジャーの成長を促していく、まさに伴走型のサービスであり、私の考えにぴったりでした。ワンストップで2年のプログラムを受けられるのは大きな決め手になった部分です。
また、私は「言葉を揃えること」を重視していました。今回は特に、一定期間並走するような施策にしたかったのですが、複数社の研修を導入すると、研修間で言葉のズレが生まれる可能性があります。そうなると、私たちが言葉の違いを理解し、それを統一して伝えていかなければいけません。この作業はとても大変ですし、労力もかかります。今回、リンクアンドモチベーションからご提案いただいたサービスなら、一気通貫でのサポートを受けられるため、言葉が揃っているだろうというイメージを持てたことも決め手の一つになりました。

年5回の研修と継続的な振り返りで行動変容を促す
「管理職支援の取り組み」
福井氏:現在実施しているマネジメント育成プログラムは、年間で5回の研修受講と、初回研修時に一人一人が立てた目標(自身のマネジャーとしてのあるべき姿)に向けた日々の現場実践とで構成されます。初回と最終回の研修の前には、360度サーベイを実施します。初回研修ではサーベイ結果をもとに受講者が自身の目標を立て、最終回の研修ではサーベイ結果から自身のビフォー・アフターを上司と部下の目線から確認することができます。年5回の研修の大まかなテーマは決まっていますが、毎回、実施前にディスカッションをして、「こういう内容でいきましょう」というようにすり合わせをしています。このディスカッションがあるおかげで、当社の意図をうまく汲んでいただいた内容になっていると思います。
研修を受講しているマネジャーの行動変容を促すためには、振り返りが欠かせません。そのため隔週で振り返りをおこない、各自がクラウド上に入力をします。クラウドには自動で振り返りを促す機能があって便利なのですが、どうしても相対的に業務の優先度が上がってしまい振り返りの入力が遅れてしまうマネジャーもいます。そのため振り返り期限の翌日にクラウドを確認して、未入力のマネジャーをチャットでフォローしています。こうしたフォローや受講者の頑張りもあり、これまでの振り返りの入力率は毎回100%で、リンクアンドモチベーションの担当者さんに驚きを持って賞賛されたのは嬉しい出来事でした。
上司や部下など、周囲から見てもマネジャーにポジティブな変化が
「取り組みの成果」
福井氏:研修が終わった後、受講したマネジャーにアンケートをとったり、直接話を聞くこともありますが、「良かった」「ためになった」という声は多く聞かれます。また、こまめに振り返りをしていることもあり、マネジャーが実際に行動に移していることもうかがえます。
マネジャーの上司に当たる部長陣からも、「行動が変わってきた」というコメントがありましたし、部下からのアンケートでも、マネジャーの変化をポジティブに受け止めている声が挙がっています。このように、周囲がマネジャーの変化を感じ取っていることからも、ジワジワと成果が出てきていることを実感しています。
例えば、研修を受講する前までメンバーに対して手取り足取り指示をする、いわゆる「マイクロマネジメント」をしていたマネジャーがいました。通常、組織のメンバーのスキルや仕事の進め方の好みは一人一人異なります。そのため、マイクロマネジメントは指示待ちの姿勢につながったり、もっと任せて欲しいのに任せてもらえないといった不満を抱くメンバーが出てしまうことがあります。マネジャー自身も理解はしていましたが、改善のキッカケを探している状況でした。
そんな中で、本プログラムの360度サーベイによってマイクロマネジメントで陥りがちな傾向が見えたこと、また研修によって改めて知見を得たことをきっかけにマネジメント方法を改善していきました。現在では「メンバーに任せられるようになった」と言っています。さらに、任せることで生まれた時間を部下とのコミュニケーション量を増やすことに使い、組織全体としても良い雰囲気が生まれてきたとも言っていました。このマネジャーの組織のように、各職場で徐々に変化が見え始めています。
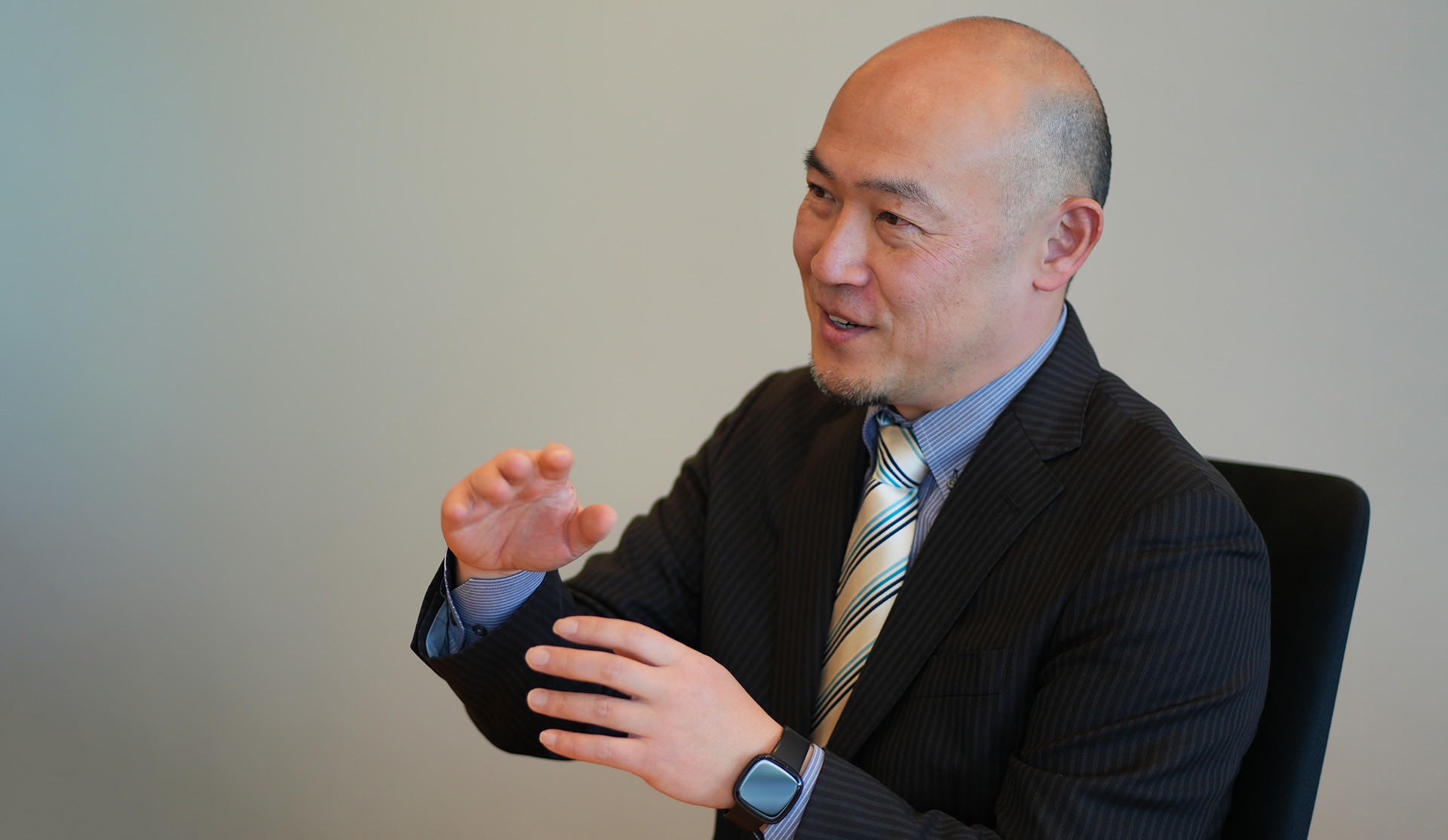
個別の業務課題に対応した実践的な学びを得られる
「リンクアンドモチベーションに感じる価値」
福井氏:リンクアンドモチベーションの研修は、1回目で「マネジャーはこう在るべき」という考え方や価値観をインプットしていただけたのが、すごく良かったです。そのうえで2回目以降、各論として「HOW」をインプットしていただけたことで、具体的な動きにつながりやすくなっていると思います。受講者が先に「在り方」を理解したことで、各論で与えられた「道具」をうまく使えているなという印象です。
特に、アドバイススクランブル(サーベイ結果を基に参加者同士でアドバイスし合う、研修内のプログラム)には大きな価値を感じています。一般的な研修でもワークショップはありますが、どんな参加者でも想像しやすい、普遍的なテーマで話をすることが多いと思います。
研修で学ぶ仕事の進め方を「カレーの作り方」に例えてみましょう。大抵の場合、現場に戻ったときにこの「カレーの作り方」はすぐには役に立ちません。なぜなら、現場の業務はカレー作りよりもっと複雑だからです。研修から現場に戻って、実際にカレーを作るとなったとしても、作る相手の年齢や野菜の好みなどに合わせて、柔軟に変えることが求められます。研修で学んだ「カレーの作り方」をそのまま使うことはできないのです。
リンクアンドモチベーションのアドバイススクランブルは、実際の業務で直面している課題や悩みを相談することができ、具体的なアドバイスをいただけます。個別の業務課題に対応した学びを得られるのは、大きなメリットではないでしょうか。一般的な研修では、学んだことを自ら抽象化し、自身の業務に応用することが必要ですが、アドバイススクランブルはそもそも自身の業務や考え方を対象にできるため、より実践的な学びを得られます。
事務局の立場から感じる価値もあります。クラウドの機能面で言えば、360度サーベイを実施するときはCSVファイルをアップロードすればすべてのデータが反映されますし、自動送信のフォローメールを設定することもできます。また、360度サーベイは関係者が多くなりますが、変更の必要があれば1人でも2人でも柔軟に変更できます。事務局にとって、非常に使い勝手が良い便利なシステムだと感じています。

自ら学ぶ文化をつくり、リスキリング推進室が不要になるのが理想
「今後目指していきたい成果、組織像」
福井氏:現在受講中のマネジャーは全体の一部のため、来期は他のマネジャーから積極的に研修を受講したいと手を挙げてくれる人が出て欲しいと思っています。
マネジャー育成の取り組みを通して、短期的にはマネジメントに対する全マネジャーの本質的な「考え方」とそれを指す「言葉」が揃っている状態を目指しています。それが、やがて組織の文化になっていくと考えているからです。「文化は戦略に勝る」と言われている通り、組織文化を醸成し定着させていくことが、長期的に目指したい方向性です。
最終的に目指したいのは「リスキリング推進室はもう要らない」と言われる状態です。一人一人の従業員が自主的に学んでいれば、わざわざリスキリングを推進する必要はありません。事業が変わるのであれば、誰に何を言われなくても必要な知識・スキルを習得し、自律的に成長していくようなイメージです。私の立場からすると、自分が用無しになるために仕事をしているようなものですが、自ら学ぶ組織づくりのためにこれからも尽力していきたいと思います。