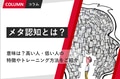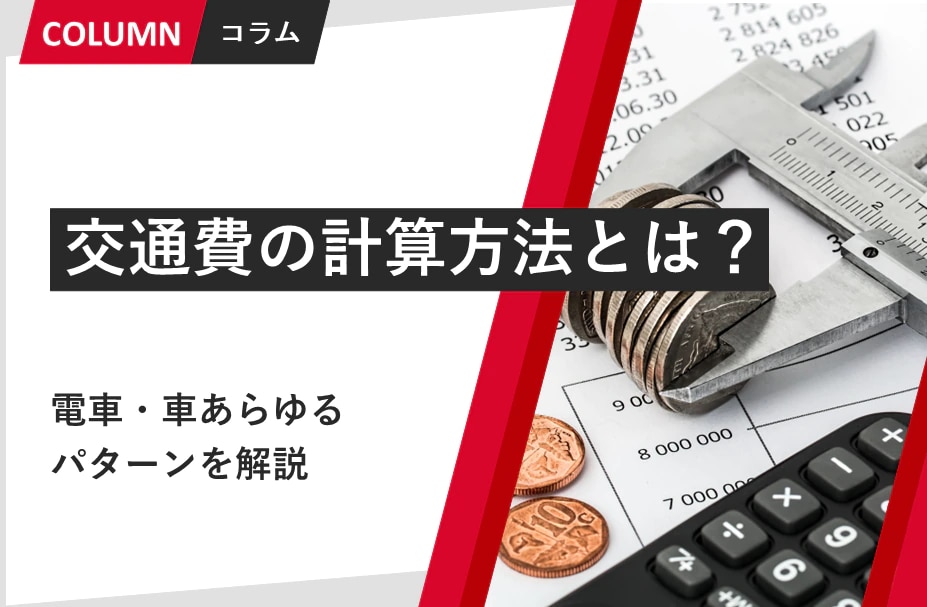
交通費の計算方法を解説!決め方や税金・社会保険料との関係、注意点などを紹介
交通費の支給条件や計算方法は、基本的に会社が自由に決めることができます。ただし、極端に従業員にとって不利なものや複雑性の高いものだと運用時のミスが増え不満のもとになる可能性もあります。(このように存在してもプラスにはならないが存在しないとマイナスを生むことを衛生要因と呼び、交通費申請も衛生要因の一つになることが多いです。)そのため、就業規則で明確なルールを定めるとともに従業員に正しく周知しておくことが重要です。今回は交通費支給のパターンや計算方法、交通費にかかる税金などについて解説していきます。
目次[非表示]
- 1.そもそも交通費とは?
- 2.交通費支給のパターン
- 3.交通費規定の内容
- 4.交通費の計算方法
- 5.交通費計算サービス
- 6.交通費と税金
- 7.交通費の非課税上限額について
- 8.出張など通勤以外の交通費について
- 9.交通費計算における注意点
- 10.出張などの旅費交通費を支払う際の注意点
- 11.まとめ
- 12.交通費計算に関するよくある質問
そもそも交通費とは?
交通費には以下の二種類があります。
通勤交通費
通勤交通費は、従業員が自宅から職場までの移動に使用する交通費を指し、多くの企業が支給する一般的な福利厚生の一つです。この交通費の目的は、従業員が仕事に通うための経済的負担を軽減することにあります。
企業によっては、公共交通機関の利用に限定して支給する場合が多いですが、車やバイクなど私用車両の利用に対して支給する場合もあります。支給の形態は、実費支給や定期券の形で提供されることが一般的で、従業員が利用する交通機関の種類や距離によって金額が決定されます。
旅費交通費
旅費交通費は、出張など仕事の目的で遠隔地へ移動する際に発生する交通費を指します。この費用は、従業員が業務の遂行のために必要な交通手段(飛行機、電車、タクシー、レンタカーなど)を利用する場合に企業が負担します。
旅費交通費の支給は、出張が頻繁に必要とされる職種において特に重要であり、従業員が業務を効果的に遂行できるよう支援します。支給範囲や方法は、企業の規定や出張政策に基づき、通常、出張の前に承認を得た後に支給されるプロセスを経ます。
交通費支給のパターン
会社が従業員に通勤のための交通費を支給する場合、そのパターンは大きく「全額支給」「一部支給」「一律支給」の3つに分けられます。
全額支給
通勤にかかるすべての交通費を支給するパターンです。従業員の負担は一切ありませんが、会社側の負担は大きくなります。
一部支給
「1日に500円まで」「1ヶ月に2万円まで」というように上限額を設けて交通費を支給するパターンです。
一律支給
「1ヶ月あたり3万円」「1日あたり1,000円」など、日単位・月単位で一律の交通費を設定し、その全額を従業員に支給するパターンです。会社側は、従業員ごとに交通費を計算する手間がかからないのがメリットです。
交通費規定の内容
交通費の支給条件や計算方法などは、それぞれの会社の裁量に委ねられています。従業員とのトラブルを防ぐためには、就業規則などに交通費規定を定めておくことが重要です。交通費規定では通常、以下のような項目について定めます。
・交通費の支給対象者
企業は、全従業員や特定の条件を満たす従業員(例:正社員、契約社員、パートタイム等)を対象に交通費を支給するかを定めます。通常、勤務地への通勤距離が一定以上である従業員が対象となることが多いです。
・交通費の支給対象者の通勤手段(電車・バス・自動車など)
企業は、支給対象となる通勤手段(電車、バス、自動車など)を指定します。これには公共交通機関のみ、または私用車や自転車の利用も含めるかを明確に定義する必要があります。
・交通費の支給金額の計算方法
支給金額は、通勤距離、選択された通勤手段、利用する交通機関の料金に基づいて計算されます。多くの企業では、最も経済的なルートと交通手段に基づいて支給額を決定します。
・交通費の支給方法(現金・定期券など)
支給方法には、現金支給や定期券の購入、または電子マネーへのチャージなどがあります。これには、毎月の給与日に支給する方法や、実費精算の形式をとるなど指定します。
なかでも、交通費の計算方法は細かくルールを定めておく必要があります。たとえば、自動車で通勤する従業員に対しては、自宅から会社までの距離に応じて交通費を支給するのが一般的ですが、距離をベースに計算するのか、ガソリン代をベースに計算するのかは会社によって異なります。また、電車やバスで通勤する従業員の場合、最も合理的な通勤経路を定めて交通費を計算するのが通常です。
交通費の計算方法
主な通勤手段ごとに、交通費の計算方法をご説明します。
マイカー通勤の場合の交通費の計算方法
マイカー通勤の場合の交通費は、以下のいずれかの方法で計算するのが一般的です。
・ガソリン単価と燃費で計算
片道の通勤距離 × 2 × 勤務日数 × ガソリン単価 ÷ 燃費
・通勤距離で計算
片道の通勤距離 × 2 × 距離単価 × 勤務日数
※距離単価は「1kmあたり10円」など、会社が任意で定めます。
電車・バスにおける交通費の計算方法
電車やバスを利用する場合の交通費は、通勤定期券による運賃相当額を支給するのが一般的です。なお、最近はテレワークの普及にともない、交通費を出勤日数に応じた実費精算に切り替える会社も増えています。
自転車や徒歩出社における交通費の計算方法
会社から近い場所に住んでいる従業員は、自転車や徒歩で通勤するケースもあります。このような従業員に交通費(通勤手当)を支給するかどうかは、会社が任意で決めることができます。支給する場合は、たとえば「片道2km以上の場合に限る」などと条件を設けたうえで、マイカー通勤の場合と同様に「片道の通勤距離 × 2 × 距離単価 × 勤務日数」で計算するケースが多いようです。
交通費計算サービス
定期代を支給する場合も、従業員から申請のあった交通費や経路をチェックする場合も、以下のような交通費計算サービス・アプリを利用するのが便利です。
駅探乗換案内
駅探乗換案内は、完全無料の乗り換え案内サービスです。電車・バス・飛行機の料金を計算できるほか、運行情報、路線図、駅の構内図や出口案内などの情報も充実しています。メンバー登録をすれば、駅や路線の登録、定期区間控除や交通費保存が可能になります。 >> 駅探乗換案内はこちら https://ekitan.com/
乗換NAVITIME
乗換NAVITIMEは、鉄道や路線バスのほか、飛行機、高速バス、フェリーの乗換ルートや所要時間、運賃を検索できるサービスです。IC運賃、定期券料金、時刻表、始発・終電、運行状況、駅周辺の地図などを確認することもできます。 >> 乗換NAVITIMEはこちら https://www.navitime.co.jp/transfer/
交通費と税金
会社から支給された通勤交通費は従業員の「所得」として所得税の課税対象になります。しかし、一定額までは所得とみなされず、非課税になるルールがあります。所得税が非課税になる条件は通勤手段によって異なり、通勤手段ごとに非課税限度額が決められています。
電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合
電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。なお、この金額が1ヶ月あたり15万円を超える場合は、15万円が非課税限度額となります。
ここで重要なのは、「最も合理的かつ経済的な経路・方法であるか?」ということです。たとえば、新幹線や特急列車を利用しても、それが最も合理的かつ経済的な経路・方法だと判断されれば非課税対象になります。一方で、グリーン車を利用するのは最も経済的かつ合理的な経路・方法とは認められないため、グリーン料金は課税対象となります。
マイカー・自転車で通勤している場合
マイカー・自転車で通勤している従業員の1ヶ月あたりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて以下のように定められています。
片道の通勤距離 |
1ヶ月あたりの非課税限度額 |
2キロメートル未満 |
0円(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円 |
55キロメートル以上 |
31,600円 |
たとえば、片道の通勤距離が12kmの場合、1ヶ月あたりの非課税限度額は7,100円となります。7,100円を超えて交通費を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。
電車やバスなどの交通機関のほか、併せてマイカーや自転車なども使って通勤している場合
駅まで自動車で行き、駅から電車に乗り換えて通勤するようなケースが対象です。この場合、非課税限度額は、以下の(1)(2)を合計した金額です。ただし、1ヶ月あたり15万円が限度になります。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月あたりの非課税となる限度額
※参考:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
※参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
交通費の非課税上限額について
交通費の非課税上限額とは、従業員に支給する交通費のうち、所得税が課せられない金額のことです。上述のとおり、公共交通機関を使って通勤している従業員の場合、「最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」が非課税となりますが、その上限は1ヶ月あたり15万円とされています。また、マイカーや自転車で通勤している従業員の場合、片道の通勤距離に応じて上限額が定められています。非課税上限額を超えて交通費が支給された場合は、超えた部分ついて所得税が課せられます。
交通費が非課税になるためには、その方法や金額が「合理的」かどうかがポイントになってきます。通常、新幹線代は非課税になりますが、グリーン車の料金は課税対象になります。なお、徒歩で通勤している従業員に交通費を支給している場合、その全額が課税対象になります。
交通費と社会保険料の関係性
上述のとおり、通勤のための交通費は非課税限度額の範囲内であれば所得税の課税対象にはなりません。一方で、通勤のための交通費は社会保険料の算定基礎となる標準月額報酬に含める必要があるのでしょうか? 結論としては、交通費を標準月額報酬に含めて社会保険料を計算する必要があります。
交通費の非課税限度額が設けられているのは、通勤にかかる費用の補てんは純粋な所得ではないと考えられるからです。一方、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額は、あくまでも会社が支払った金額を基準とするため、交通費も含まれます。つまり、交通費の支給額が大きい従業員ほど、社会保険料の負担も大きくなります。
▼社会保険に関する記事はこちら
社会保険とは?加入条件や雇用保険との違い、メリット・デメリットを解説!
出張など通勤以外の交通費について
交通費は、厳密に言うと「通勤手当」と「旅費交通費」に分けられ、出張や外回りのための交通費は旅費交通費に該当します。旅費交通費は通勤手当と異なり、会社が当然に負担すべき費用であり、従業員が立て替えた金額を会社に請求して精算するのが一般的です。
通常、出張や外回りのために交通費を立て替えた従業員は、旅費交通費精算書を作成して経理部門に提出します。公共交通機関は領収書が発行されないため、経理部門は旅費交通費精算書をチェックして、「経路は適切か?」「金額に誤りはないか?」などを確認します。タクシーを使ったときは領収書を添付するのが通常です。そのうえで、都度精算、もしくは月次で清算するのが一般的です。
交通費計算における注意点
交通費計算における注意点としては、就業規則や賃金規定を明確に規定することや不正受給を防止することなどが重要です。
就業規則や賃金規定を明確に定める
従業員に支給する交通費に関するルールは、就業規則に定めておくことが重要です。できるだけ詳細に規定しておくことで、従業員の不満や無用なトラブルを防ぐことにつながります。交通費について就業規則に定める際のポイントは、以下のとおりです。
・支給対象者や支給要件
雇用形態や交通手段、通勤距離などによって交通費を支給するかどうかを規定します。
・支給金額や支給限度額
公共交通機関を利用する場合、1ヶ月あたり15万円が非課税上限額であることを明記します。また、マイカーや自転車などを利用する場合、通勤距離によって異なる非課税上限額を明記しておきましょう。
・支給方法や支払時期
交通費を毎月の給与と合わせて現金で支給するか、現物(定期券)で支給するかを規定します。また、前払いか後払いかも規定しておきます。
・有給取得時の支給の有無
有給取得時は会社に出勤しないため、交通費はかかりません。この場合に交通費を支給するかどうかを規定します。
不正受給が無いようにする
交通費に付いてまわる問題が不正受給です。たとえば、交通費を受け取りながら自転車で通勤するなど、実際に発生していない交通費を請求することで不正受給するケースがあります。また、実際には交通費が安い経路で通勤しているにもかかわらず、高い交通費の経路で申請し、差額を不正受給するケースも少なくないようです。不正受給があると会社にとって損失になるだけでなく、従業員との信頼関係が大きく損なわれるため、不正受給が起きないような体制を整えることが重要です。
そのためには、会社として明確なルールを定めておかなければいけません。利用可能な交通手段や交通費負担の範囲、申請時期や申請方法、支給対象者や支給要件、支給金額などのルールを明確に定めましょう。また、交通費を不正受給した場合の返還義務や罰則についても規定して従業員に周知すれば、不正受給の抑止力になるはずです。そのうえで、適切な監査・教育をおこない、不正受給が起こらない体制を整えましょう。
▼関連記事はこちら
リスクマネジメントの意味とは?企業に必要な理由や具体的な方法を解説
不正受給が発覚した際の対応
交通費の不正受給が発覚した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。まず、関係者に対して事実確認を行い、不正の詳細を把握します。このプロセスでは、受給した交通費の領収書や移動履歴などの証拠資料の確認が必要です。
事実が確認できたら、不正受給した金額の返還を求める必要があります。また、企業や組織によっては、規定に基づいた懲戒処分が行われる可能性があります。さらに、内部統制システムの見直しや、従業員への研修を実施して再発防止策を講じることが重要です。
▼関連記事はこちら
インシデントとは?【 わかりやすく】意味やアクシデントとの違いについて解説
在宅勤務(テレワーク)の精算
最近はテレワーク・在宅勤務を導入する企業が増えていますが、その際に見直しが必要になるのが交通費です。テレワーク・在宅勤務を導入する場合の交通費については法令の定めがなく、その対応は各企業に委ねられています。一般的には以下のような対応が考えられます。
・従来どおりの交通費を支給する
テレワーク・在宅勤務が一時的なものである場合や出社日数が多い場合などは、従来どおりの交通費を支給しても構いません。
・支給額を減額する
テレワーク・在宅勤務が長期的なものである場合や出社日数が少ない場合などは、交通費を減額して支給することも考えられます。
・支給期間を短縮する
たとえば、6ヶ月の交通費をまとめて支給していた会社が、テレワーク・在宅勤務導入後に1ヶ月ごとの支給にするケースも考えられます。
・実費精算に切り替える
テレワーク・在宅勤務を導入していても、一定の割合・日数で出社勤務をする企業も少なくありません。このような場合、出社日数に応じて交通費を実費で支給することも可能です。
ルール変更の際は就業規則の変更を
交通費の支給ルールが変更になる際、多くの場合、就業規則の改定が必要です。就業規則は従業員に対する労働条件や会社の規定を定める重要な文書であり、交通費の支給基準もその一部を形成します。ルールの変更は、従業員の経済的利益に直接影響を及ぼすため、改定には慎重な手続きが必要です。
まず、変更の内容を明確にし、労働者代表との協議を経て合意を形成することが大切です。合意が得られた場合、就業規則の変更内容を文書化し、労働基準監督署への届出が必要となります。また、変更後のルールを従業員に周知し、理解を促すための説明会や文書配布などが重要です。
▼関連記事はこちら
ガバナンスとは?意味やコンプライアンスとの違い、強化する施策、事例を解説
出張などの旅費交通費を支払う際の注意点
事前の承認と予算の確認
旅費交通費を支払う前に、すべての出張が事前に承認されていることを確認することが重要です。出張の目的、期間、および必要な交通手段を明確にし、これらが会社の出張ポリシーに準じているかを検討する必要があります。
また、予算の範囲内で計画を立て、不必要な支出を避けるために最もコスト効率の良い選択肢を選ぶことが求められます。事前承認プロセスによって、出張が業務の目標と整合性を持っていることを保証し、予算オーバーランを防ぐことができます。
領収書と実費精算の厳格な管理
旅費交通費を支給する際には、従業員が提出する全ての領収書が正確で、必要な支出の証明として適切であることを確認する必要があります。領収書の管理は、会社の財務記録の正確性を保ち、税務上の問題を避けるためにも重要です。
支出が実際に業務の遂行に必要だったかを検証し、私的な支出が交通費として請求されていないことを確認します。また、従業員に対して、旅行終了後迅速に全ての領収書と共に経費報告書を提出することを義務付けることで、経費の透明性と追跡が容易になります。
まとめ
昨今は、テレワーク・在宅勤務が増え、交通費の取り扱いを見直す企業が増えています。交通費の取り扱いを変更する場合は、支給条件や計算方法を明確に定めるとともに従業員に正しく周知して、従業員が交通費申請をする際に迷いが発生することを防ぎましょう。
交通費計算に関するよくある質問
Q:マイカー通勤の高速道路代は交通費の非課税対象になる?
非課税対象になるかどうかはケースバイケースであり、通勤経路・方法の合理性や経済性を個別に検討する必要があります。高速道路を使うことが、最も合理的かつ経済的な経路・方法であると認められれば、高速道路代も非課税対象になります。
Q:交通費の不正受給を防ぐには?
就業規則に、支給条件や不正があった場合の罰則を明記しておくことが重要です。条件・ルールがあいまいだと不正が起こりやすく、従業員に不正の口実を与えることになってしまいます。不正が発覚した場合の対応としては、「全額を返金する」「懲戒処分とする」などの規定を設けておくのが良いでしょう。