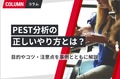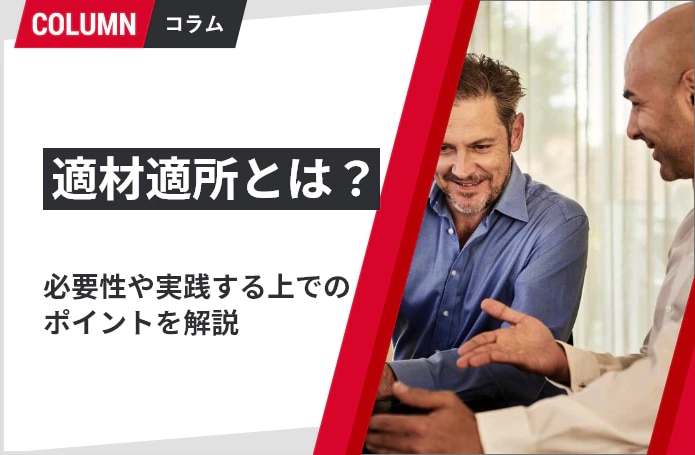
適材適所とは?ビジネスにおける意味や使い方、メリット、人材配置の方法を簡単に解説
「適材適所」は古くからある考え方ですが、近年、組織の人材配置においてあらためて適材適所の重要性が注目されています。今回は、適材適所を実現するために必要なことや、適材適所の人材配置がもたらすメリットなどについて解説していきます。
目次[非表示]
ビジネスにおける適材適所とはどういう意味?
「適材適所」と「適所適材」の違い
「適材適所」とは、適した人材を適切な位置に配置することを意味します。これは、個々の能力や特性を考慮し、最も効果的に活躍できる場所に人を割り当てる経営戦略です。
一方、「適所適材」は、この言葉を逆にしたもので、特に定義された意味はありませんが、場所や状況に応じて適切な人材を見つける、と解釈されることがあります。しかし、一般的には「適材適所」が正しい用法とされています。
適材適所の使い方・例文
「適材適所」は、人の能力や適性を考慮して、最適な位置に配置するという意味で使います。
例文:「新プロジェクトの成功の鍵は、メンバーの適材適所な配置にある。彼の経験と技能を生かすため、リーダーに任命した。」この例では、特定のメンバーが持つ経験や技能を最大限に活かすために、リーダーのポジションに配置するという意思決定を表しています。
■適材適所が求められる理由
適材適所は古くからある考え方ですが、近年、組織の人材配置においてあらためて適材適所の重要性が注目されています。その背景を解説します。
労働力不足
少子高齢化によって労働人口が減少し、どの企業にとっても人材確保が難しい時代になっていますが、そのような環境下でも、企業は競争力を高めていかなければいけません。そのためには、従業員の業務適性を見極め、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる適材適所の人材配置が不可欠です。
働き方の多様化
働き方改革の推進により、企業には多様性のある働き方への対応が求められるようになりました。たとえば、子育てや介護を理由として離職する人は少なくありませんが、子育てや介護と仕事を両立できる会社なら優秀な人材の離職を防止できます。
このように、「子育て・介護と両立しながら働く」「副業しながら働く」「在宅で働く」など、働き方の多様化に対応するためにも適材適所の人材配置が求められるようになっています。
これまでのように、従業員を会社のやり方に合わせるのではなく、個々の従業員が希望する働き方や在りたい姿に合わせて適材適所の人材配置ができれば、企業の競争力強化にもつながるはずです。
ここまで、「適材適所」が必要になった社会的な背景をご紹介しました。ただ、企業の適材適所の実現は簡単なことではありません。現在はVUCA時代という、社会やビジネスなどあらゆるものを取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難になっている時代です。
今の会社の事業内容や人数規模に合わせた短期目線での適材適所の実現だけでなく、長期的な会社の競争力を育むための意欲・能力開発も同時に必要です。ここからは、「短期的な適材適所の実現」と「継続的・長期的な適材適所の実現」のために必要なことの両面を紹介していきます。
短期的な視線で考えたときに、個人の得意領域が活かせ、成果創出できるところに配置することは、個人のモチベーションにも繋がり、業績の向上にも寄与します。
適材適所の人材配置がもたらす効果・メリット
適材適所の人材配置をすることで、企業には以下のようなメリットが期待できます。
■生産性の向上
「好きこそ物の上手なれ」と言うように、自分が好きな業務・得意な業務に携わることができれば、従業員はスピードの面でもクオリティの面でも優れたパフォーマンスを発揮できます。 また、好きな仕事・やりたい仕事を任せてもらえればモチベーションも上がるので、必然的に短期的な生産性や業績の向上につながっていくはずです。
■離職率の低下
ビジネスパーソンにとって、苦手な仕事や嫌いな仕事を克服するのは重要なことですが、必ずしもうまくいく人ばかりではありません。 長期間、成果が上がらなければ自信を失い、その仕事を続けることが苦痛になり、結果的に離職に至るケースも少なくありません。逆に、適材適所の人材配置ができており、スキルや志向にマッチした仕事が与えられていれば高いモチベーションを保って働くことができるため、離職の防止につながります。
■コストの削減
適材適所の人材配置ができていないと、従業員はモチベーションを維持するのが難しく、パフォーマンスも低下しがちです。そのために組織全体の生産性が低下して、それを残業や人員補充でカバーすることになれば人件費も増加します。 また、モチベーションを失った従業員が離職してしまえば、欠員補充のための採用コストがかかります。適材適所の人材配置ができていれば、このような人件費・採用コストの無駄を削減することができます。
■市場変化への適応能力の向上
その従業員が得意とする領域に配置するだけでなく、従業員本人が伸ばしたいと思っているスキルや潜在的に伸びる可能性のあるスキルを伸ばせる部署へ配属することは、市場変化への適応能力向上に繋がります。 同じ領域を得意とする人たちばかりが集まっていると、世の中のニーズが変化してきた場合に必ずしも適応できるとは限りません。 しかし、そのスキルを伸ばしたいと思っている従業員や、潜在的に伸ばせる可能性のある従業員が配属されていると、その部署で必要とされるスキルや能力以外の力を持っているため、予期せぬ変化が訪れたときに柔軟に対応できる可能性が高まります。 メリットの①~③は、その領域が得意な従業員を配置することで、生産性や業績向上に繋がるので短期的な大きなメリットですが、見込のある者を配置することは長期的にメリットがあります。
■採用ミスマッチの防止
適材適所の人材配置をおこなうためには、採用時からそれぞれの候補者のスキルや経験を評価し、最適なポジションでの活躍がイメージできる人材を採用する必要があります。そうすることで、入社した人材はスムーズに仕事に適応でき、自身の能力を最大限に活かしながら働くことができます。また、一人ひとりの興味や価値観、キャリアプランにも配慮した配置をおこなうため、やりがいを感じながら高いモチベーションで働くことができます。結果的に定着率が高まり、採用のミスマッチ防止につながります。
適材適所の人材配置がもたらすデメリットは?
適材適所の人材配置がもたらすデメリットについてご説明します。適材適所の人材配置は企業にとってメリットが多い一方で、実施するにあたって注意すべきポイントもあります。
■ 従業員の成長を妨げる可能性がある
一般的に、適材適所の人材配置は従業員の成長や組織のパフォーマンスにプラスの影響をもたらすと考えられています。ただし、短いスパンで人材配置がおこなわれると、逆に従業員の成長が阻害されてしまうおそれもあります。配置が変わった従業員は十分な時間をかけて新しい役割に慣れ、チーム内での関係性を構築していく必要があるため、短いスパンで人材配置が繰り返されると、「慣れたと思ったらまた異動」ということになり、思うようなパフォーマンスを発揮することができません。また、頻繁な人材配置がおこなわれると、従業員が特定の業務領域における専門性を獲得するのが難しくなるほか、キャリアパスの方向性を見いだすのも困難になってしまいます。
■ 短期的に生産性が低下するおそれがある
人材配置を変更した場合、異動になった従業員は新しい役割やチームに慣れる必要がありますが、そのためには決して少なくない時間がかかります。新しい役割やプロジェクトにおいて必要な情報・知識が不足している場合は、当然のことですが情報収集や学習が必要になり、そのためにも時間がかかります。また、人材配置の変更がチーム全体やプロジェクト体制に影響を及ぼす場合、チーム内の役割分担や業務フローの再構築を余儀なくされることもあるでしょう。適材適所の人材配置は長期的に見れば、組織全体の生産性を高める取り組みだと言えますが、短期的には生産性が低下することも少なくありません。そのことも念頭に置いたうえで、人材配置の変更を検討しなければいけません。
■ 従業員が精神的な負担を強いられることがある
人材配置の変更により、異動になった従業員は新しい役割や責任を引き受けることになります。それまで慣れ親しんだ環境・業務から離れ、新しい役割・業務に適応するためには時間がかかるだけでなく、未知の領域に踏み出すことにともなう不安やストレスも生じるはずです。また、人材配置の変更によって異動になった従業員は、一般的に大きな期待が寄せられるものです。異動先で周囲から大きな期待が寄せられるため、成果に対するプレッシャーも増大します。このようなストレスやプレッシャーから精神的な負担を感じ、新しい環境にうまく適応できなかったり、期待されていたパフォーマンスを発揮できなかったりするケースも少なくありません。
適材適所の人材配置をする方法・手順
適材適所の人材配置をするためには、以下のようなプロセスが必要です。
■業務の内容や課題を洗い出す
適材適所の人材配置をおこなうためには、まず業務の棚卸しをする必要があります。自社の業務をすべて洗い出すとともに、業務課題を抽出します。業務内容や業務課題を可視化することで、どの業務、もしくはどの部署にどのような知識・経験・スキルを持った人材が必要なのかが見えてくるでしょう。
■従業員の能力・スキルを見極める
従業員の能力・スキルを見極めることも不可欠です。その際は、スキルマップを活用するのも良いでしょう。スキルマップとは、従業員が業務を遂行するうえで必要な能力・スキルを有しているかどうかを記録し、可視化するツールです。
一人ひとりの従業員のスキルを客観的に把握することは、適材適所の人材配置だけでなく正当な人事評価にもつながります。
一方、得意な能力やスキルのみで人材配置を検討すると、長期的に見たときに個人がキャリアに対して頭打ちになっていると感じ、成長実感を得られなくなる可能性があります。スキルマップを作成する場合は、現在保有している能力・スキルだけでなく、潜在的な能力・スキルなども記録するようにしましょう。
■従業員の価値観や希望を把握する
従業員が既に保有している能力・スキルだけでなく、従業員が「どんな価値観を持っているのか?」「どんな働き方をしたいのか?」「どんな志向があり、何を実現したいのか?」といったことを把握することも大切です。
従業員の価値観が多様化する現代においては、一人ひとりの従業員と向き合って価値観や希望を把握したうえで、人材配置に反映していかなければいけません。
短期的にはその部署で必要とされる能力やスキルを保有していなくても、配置されることで伸ばしていくことは可能です。将来的な環境・ニーズの変化に対応できる組織にするためにも、本人が獲得したいと思っている能力やスキルを把握し、配置に反映することは大切です。
■定期的なフォローアップをする
適材適所の人材配置をおこなった後は、定期的なフォローアップをしていかなければいけません。新しい環境・ポジションにおいては、初めての業務や人間関係に戸惑い、精神的な負担からメンタル不調に陥ってしまう従業員もいます。このような事態を避けるためにも、適切なフォローアップをおこなう必要があります。また、人材配置をおこなった後は、対象者の将来のキャリアパスを再整理する必要があります。フォローアップの際は、対象者の目標設定をおこなうとともにキャリアの方向性を確認し、成長を促していくようにしましょう。
近年は「OKR」と呼ばれる目標管理方法が注目されています。OKRに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
>> 目標管理とは?行動振り返り、MBO、OKRを詳しく解説
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0050
また、フォローアップに関しては以下の記事も参考にしてください。
>> フォローアップとは?重要性や取組み方、研修内容例を紹介
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0109
適材適所の人材配置に役立つ施策
適材適所の人材配置をおこなうためには、以下のような施策が役立ちます。
■適性検査
上述のとおり、適材適所の人材配置を実現するには、従業員の能力や性格を把握することが大前提になります。その際に役立つのが適性検査です。
上司・マネジャーの主観が入り込まないのが適性検査の利点であり、従業員のパーソナリティや志向性、ストレス耐性などを客観的かつ定量的に把握することができます。
■1on1などの面談
従業員のスキルや経験、適性検査の結果など、客観的なデータだけを根拠に人材配置をしても、適材適所を実現するのは難しいでしょう。
定量的な情報だけでなく、定性的な情報も把握したうえで人材配置を検討しなければいけません。そのためには、1on1などの面談が欠かせません。面談を通して、従業員の目標や理想とする働き方、将来の在り方などをヒアリングしましょう。
▼1on1について詳しくはこちら
1on1とは?効果的な進め方やテーマ例、失敗原因まで紹介
1on1ミーティングの前に確認したい「部下との関係性」
■従業員情報のデータベース化
従業員数が多いほど、また組織体系が複雑なほど、適材適所の人材配置をするのが難しくなります。このような場合、従業員情報をデータベース化するのがおすすめです。各従業員のスキルや経験、保有資格はもちろん、面談でヒアリングした価値観や要望なども集約することで、短期的にも長期的にも適材適所の人材配置の判断をしやすくなります。
短期的には、モチベーションが下がっている社員を得意な能力を活かせる部署へ配置、業績が下がっている部署にはその領域の得意な社員を配置するといった対応ができます。
長期的には、本人が希望するスキルを向上できる部署へ配置するなど、社員のモチベーションアップだけでなく、会社としても変化へ柔軟に対応できる人材の育成につなげることが可能です。
■ジョブローテーション
ジョブローテーションとは、期間を決めて従業員の業務内容や職種を変える人事施策のこと。従業員に様々な業務経験を積ませることで人材育成を図る手法として一般的ですが、適材適所の人材配置をおこなう手がかりを得るのにも効果的です。
ジョブローテーションをした従業員は多様な業務経験を通して、自らの適性を再確認したり、自分でも認識していなかった適性を発見したりすることができます。それは、今後市場のニーズに変化が起こり、適応していかなければならない状態になった際の人材配置にも役立ちます。
ジョブローテーションに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
※参考: ジョブローテーションとは?メリット・デメリットや効果的な期間を解説
■従業員アンケート
従業員アンケートを実施することで、個々の従業員の要望やキャリア観などを把握することができます。このような情報は、適材適所の人材配置を検討するうえで大いに参考になるものです。また、従業員アンケートは課題を早期に発見し、改善するための手段としても役立ちます。従業員が抱える不満や悩みなどの情報を収集することで、適材適所の人材配置をおこなううえでの障害や改善点をクリアにすることも可能です。
従業員アンケートは、風通しの良い職場をつくるうえでも重要な取り組みの一つになります。風通しの良い職場に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
>> 風通しの良い職場とは?メリット・デメリットや具体的な施策案をご紹介
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0009
■副業・兼業の解禁
働き方改革の一環として、従業員の副業や兼業を認める企業が増えています。副業や兼業をすることで、従業員は本業とは異なる知識・スキルを習得することができます。
また、本業と異なる経験は、自分自身の適性や今後挑戦したいことをより明確に認識できる機会になりますし、仕事観が変わるきっかけにもなります。
副業・兼業の経験を通してひと回り成長した従業員は、新規事業を牽引するリーダーになるなど、自社においても活躍の場を広げることができるでしょう。
適材適所の人材配置を成功させた企業事例
適材適所の人材配置で成功を収めている企業として有名なのが、ソニーやサイバーエージェント、富士フイルムです。各社の取り組みをご紹介します。
■適材適所の企業事例① ソニー株式会社
ソニーには「自分のキャリアは自分で築く」という考え方が根付いており、幅広いフィールドのなかで従業員が主体的にキャリアを形成できるよう、様々な制度が用意されています。
社内募集制度
新しい挑戦をしたいという個人の意志により自ら手を挙げ、希望する部署やポストに応募できる制度です。所属部署に2年以上在籍している従業員であれば、上司の許可なく自由に応募することが可能。
社内で転職するようなイメージで自分のやりたいことにチャレンジできる、主体的にキャリアを形成するうえで欠かすことができない制度になっています。ソニーの社内募集制度はすでに50年以上も運用されており、これまで7,000名以上の従業員がこの制度を利用して異動しています。
社内フリーエージェント(FA)制度
仕事を通じて高評価を獲得した従業員に対して、プロ野球のようにフリーエージェント権(FA権)が与えられる制度です。
寄せられたポストや職種へのオファーに対して、FA権を行使することによって新しい職場へ異動することができます。この制度は2015年から導入されており、これまで1,000名以上の従業員がFA権を付与されています。
キャリアプラス制度
本来の担当業務を続けながら、業務時間の一部を別の仕事に充てることができる制度です。所属する部署から異動することなく新たな仕事やプロジェクトを経験し、キャリア展開の選択肢を広げたり、他部門で自分の専門性を活かしたりすることが可能です。
Sony CAREER LINK
ソニーグループ内で新たな業務へのチャレンジを希望する従業員と、人材を求めている部署をマッチングする制度です。上長と相談のうえ「Sony CAREER LINK」に登録すると、マッチングの可能性がある部署から面談の依頼が入り、その結果によって異動が決まります。
※参照:ソニーグループポータル | 採用情報 | グループ本社、ゲーム事業、エレクトロニクス事業、半導体事業 | 挑戦を後押しする制度
■適材適所の企業事例② 株式会社サイバーエージェント
サイバーエージェントでは、人材の能力を最大限に引き出し、適材適所を実現するために以下のような施策を導入しています。
人材覚醒会議
役員が戦略的な人事配置についてのみ話し合う場が、人材覚醒会議です。優秀な人材の最適な配置をすることで個人と事業を成長させることを目的としています。
キャリチャレ
現部署での勤続が1年以上になると、希望する他部門またはグループ会社への異動をチャレンジできる社内異動公募制度です。
キャリバー
グループ内の様々な部署の職場環境や人材ニーズを可視化したシステムです。
※参照:適材適所を叶える仕組み | 株式会社サイバーエージェント
■適材適所の企業事例③ 富士フイルム株式会社
富士フイルムは、人事管理のツールとして独自の「総合人事情報システム」を開発し、1982年(昭和57年)1月から稼動を開始しています。総合人事情報システムは、各従業員の過去のキャリアと実績、現在の専門性と保有能力、将来の育成方向、私的身上情報など個人にまつわる情報を把握し、これらの情報を記録したものです。このシステムでは人材情報の更新・検索・作表が容易にできるだけでなく、一人ひとりの従業員がより力を発揮し成長し得る、適材適所を実現するために活用されています。
※参照:富士フイルムのあゆみ 活力ある企業集団づくりと労働条件の向上、労使関係の安定化
管理職の研修等はストレッチクラウドへ
ここまで適材適所の意味や必要性、適材適所の人材配置をする際のポイントについて説明いたしました。
弊社のストレッチクラウドでは、適材適所の人材配置を行い従業員のモチベーションを維持するマネジメント人材を育てるために、 まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。
その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。 結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。
ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。
▶ストレッチクラウドの詳細はこちら
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service
まとめ
日本企業には、優秀な人材を手放したくないと自部署で抱え込もうとする傾向があり、それが適材適所の人材配置の障壁になっているケースも少なくありません。
ですが、縦割りが強い組織では、今以上の成長が見込めないのは明らかです。ぜひ、縦割りの壁を取り払い、適材適所を実現することで組織の活性化を図っていきましょう。
適材適所に関するよくある質問
Q:適材適所とはどういう意味?
適材適所とは、直訳すると「適切な材料を適切な場所に配置する」という意味になります。人材配置や人材活用のシーンで適材適所という言葉が使われるときは、個々の従業員の能力や特性を適切に把握し、それに応じた役割や仕事を割り当てることを言います。組織が適材適所の人材配置をおこなうことで、従業員の能力を最大限に引き出し、組織全体の成果を最大化することができると言われています。
Q:適材適所のメリットは?
適材適所の人材配置は、一人ひとりの従業員の能力や特性に基づいて最適な役割や仕事を割り当てることで、個々の得意分野や専門知識、スキルを活かすことを狙うものです。個々の従業員が自分の能力を最大限に発揮できる環境で働くことでモチベーションも高まるため、パフォーマンスアップが期待できます。従業員個人としては専門性に磨きをかけることでキャリアアップが促進され、組織全体としては生産性や競争力の向上につながるでしょう。