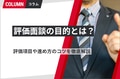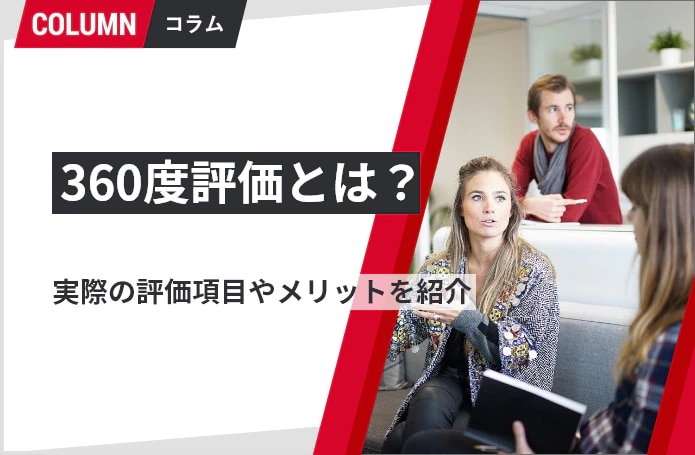
360度(多面評価)とは?実際の評価項目やメリットを紹介
テレワークの導入が急速に進み、職場でのコミュニケーションや評価方法の見直しが進んでいます。
メンバーシップ型とジョブ型の良さを掛け合わせた新しい働き方が求められる中、注目されているのが「360度評価」(多面評価)です。
職場のコミュニケーションを活性化させ、個人のパフォーマンスを引き出す鍵となる360度評価(多面評価)、そしてその評価結果を活用するサーベイ研修とは一体どのようなものなのか、ご紹介します。
目次[非表示]
360度評価(多面評価)とはなにか
「評価」の難しさを乗り越え、「成長」という目的により効果的なのが360度評価(多面評価)です。その中身や選ばれる理由、ゴールは一体どのようなものでしょうか。
360度評価(多面評価)とは
360度評価(多面評価)とは、上司だけではなく、同僚、部下の複数名から、日々の職務行動を評価する評価方法のことです。
複数名によってつけられた評価を平均することによって評価のばらつきを抑え、より客観的な結果を得ることができます。これは評価される本人に対しても評価に対する納得感を高めることができます。
周囲からの評価を求めるため、様々な関係者からの評価を集めることになりますが、下記のような評価者、目的、優先順位での調査を推奨しています。
①上司・管理職(業務の基準の確認)
②職場メンバー・部下(実際の業務の様子を把握)
③自分(周囲の認識との相対化)
④同僚・同期(よく知る仲間からの評判)
⑤顧客・関係部署(価値の提供先からの評価)
日本における360度評価(多面評価)の導入率は?
「360度評価は意味ない」という声が聞かれることもありますが、実際にはどうなのでしょうか。リクルートマネジメントソリューションズ社が実施した「360度評価活用における実態調査」では、31.4%の企業が360度評価を導入しており、今後も継続して実施/今後実施してみたい企業は50.4%に上りました。比較的多くの企業が360度評価に意義を感じていたり、興味を持っていたりすることが分かります。なお、360度評価の対象とする役職として多いのは、課長層(62.5%)、次いで部長層(59.5%)という結果が出ています。
※参考:注目の360度評価導入企業の活用実態調査から効果的な活用法をご紹介|リクルートマネジメントソリューションズ
https://www.recruit-ms.co.jp/press/pressrelease/detail/0000000304/
360度評価(多面評価)をどのように活用するか~運用事例のご紹介~
360度評価(多面評価)を成長のために用いることはご説明しましたが、実際に活用されている企業の事例もご紹介します。
①管理職の育成課題の抽出のために活用
管理職のトレーニングにおいては、知識習得形式の研修は実践しやすいものの、マネジメントの実践トレーニングをどう実施するかが問題になります。そこで管理職研修では、各管理職の課題を抽出するために、360度評価(多面評価)の結果を用いた課題解決形式を採用することが多くなってきています。
特に、既任管理職向けの研修では、360度評価(多面評価)の結果を活用することが昇格後一定期間が経った管理職に変化を促すことに繋がり、非常に有効です。
②研修効果の測定として活用
個別の課題を特定するだけではなく、研修を経た現場での変化を測定する目的で、事前事後の360度評価(多面評価)を行う企業も増えています。
管理職360度評価(多面評価)サーベイ研修では、マネジメントに変化が起き、上司が、メンバーから見た認識が変化したのかを測定することで、研修での学びを現場活用できたかを測定することができます。
③評価の参考指標として導入
直接的な評価指標としての活用にはリスクが伴いますが、「メンバーからの評価が一向に上がらないマネジャー」や「協働者との連携が全くできないメンバー」など、職場の実態が一部見える化されるのが正直なところです。
ある企業では、昇格・降格の検討の一材料として、2年分(半年に1回、3回分)の360度評価(多面評価)スコア結果を評価の参考指標として活用しています。
④状況の定点観測で運用
メンバーの変更、事業環境の変化など、同じ職場であっても状況は日々変化します。その中で「自分に今何が求められているのか」を明確にするために360度評価(多面評価)が有効です。
周囲と気持ちよく連携し、個人の能力を最大化させるために、今の課題は何なのか、周囲から何を求められ、どのように見られているのかを定期的に測り、活用する企業が増えています。
⑤職場のコミュニケーション機会として活用
普段の業務の中では、お互いに求めたいこと、感じていることをきちんと伝える機会はなかなかありません。360度評価(多面評価)では、仕事ぶりや職場で期待する役割を伝えることができるため、メンバーが互いの成長に向けて協力するために活用する企業も増えています。
360度評価(多面評価)サーベイ結果をもとに職場でコミュニケーションをとることで、成果につながるフランクなコミュニケーションをとることができます。
▼管理職の360度評価がうまくいかない4つの理由 資料はこちら
360度評価(多面評価)のメリット
360度評価を運用することで、企業にとっては多くのメリットが生まれます。360度評価により、どのような効果が見込めるのかを確認しておきましょう。ここでは、代表的なメリットについて簡単にご紹介します。
多角的な視点からの評価
360度評価は、一方的な評価では捉えきれない従業員の多面的な側面を明らかにします。従来の上司からの評価だけでは、部下や同僚、顧客との関わりやチーム内での協力の様子など、多くの側面が見逃される可能性があります。 しかし、360度評価を採用することで、これらの多角的な視点を取り入れることができ、従業員の真のパフォーマンスや潜在能力をより正確に評価することが可能となります。360度評価を取り入れることで、これまで以上に実態に即した評価を行い、従業員の成長に対する適切なサポートができるようになるでしょう。
自己認識の向上
自己評価を含む360度評価は、従業員に自らの強みや弱点を客観的に認識する機会を提供します。他者の視点からの評価を受け取ることで、自分の認識とのギャップや、これまで気づかなかった点を発見することができます。 このような自己認識の向上は、自己成長のための具体的なアクションプランの策定や、キャリアの方向性を見直す際の参考となります。キャリアに対する主体性が向上すると、仕事に対する意欲も向上しやすくなります。 また、自己認識が高まることで、職場でのコミュニケーションや協力の質も向上する可能性があります。
リーダーシップの質の向上
リーダーやマネージャーにとって、部下や同僚からのフィードバックは、リーダーシップの質を向上させるための鍵となります。360度評価を通じて、リーダーは自分のリーダーシップスタイルやコミュニケーション方法についての具体的なフィードバックを周囲のメンバーから直接受け取ることができます。 これにより、リーダーは自らの弱点を補完し、より効果的なリーダーシップを展開することができるようになります。組織のリーダーシップの質が向上することで、組織全体の成長や変革のスピードも加速する可能性があります。
組織のコミュニケーションの促進
360度評価は、組織内のオープンなコミュニケーションを奨励します。従業員同士の信頼関係が深まることで、フィードバックを受け入れやすくなり、また、他者の意見や視点を尊重する文化が育成されます。 また、周囲からの評価が定量的にまとめられたデータを見ながら対話することで、それぞれが客観的な意見を述べやすくなり、相手を責めるようなコミュニケーションになりにくくなります。あくまでお互いの成長を目的とした対話を重ねることで、そのチームではお互いのためになるフィードバックを行う文化が醸成されます。
パフォーマンスの向上
360度評価を通じて、従業員は自分の行動や成果が他者にどのような影響を与えているかを具体的に理解することができます。つまり、自分の行ったことがどのような結果になっているのか、どういう受け取り方をされているのかといったことを、客観的に把握することができるようになります。 客観的に自身の行動と成果を把握することで、自分のパフォーマンスを振り返ることができるでしょう。パフォーマンスの振り返りを定期的に行うことで、その向上に対する取り組みを行うことができます。結果として、360度評価の機会を通じてパフォーマンス向上の機会を創出することができます。
360度評価(多面評価)のデメリット
360度評価は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在しており、デメリットも把握した上で、360度評価を運用することが大切です。ここでは、360度評価の代表的なデメリットをご紹介します。
フィードバックの質のばらつき
360度評価では、多くの人々からのフィードバックを収集しますが、その質は一定ではありません。部下、同僚、上司、場合によっては顧客からの評価が含まれるため、それぞれの評価者の主観やバイアス、評価の基準が異なる可能性があります。 また、評価者が適切なフィードバックを提供するためのトレーニングやガイダンスが不足している場合、表面的な評価や抽象的なコメントが増える恐れがあります。このような不均一なフィードバックは、評価の信頼性や有効性を低下させる可能性があります。
時間とコストの増加
360度評価の実施は、従来の上司からの一方的な評価よりも時間とコストがかかる場合が多いです。多くの評価者からのフィードバックを収集、分析し、それを評価対象者にフィードバックとして伝えるプロセスは、非常に手間と時間がかかるものです。 また、評価の信頼性や有効性を確保するためのトレーニングやツールの導入にもコストがかかります。これらの時間とコストの増加は、特に中小企業やリソースが限られている組織にとっては、これまでの業務と並行して360度評価を運用することが大きな負担となる可能性があります。
人間関係の緊張や不信感の増加
360度評価は、匿名性を保持しながらも、同僚や部下からの直接的な評価を受け取ることになります。この評価が厳しいものであった場合や、期待していた評価と大きく異なる場合、評価対象者はショックを受けることがあります。 また、誰からどのような評価を受けたのかを推測することで、職場内の人間関係に緊張や不信感が生じるリスクも考えられます。このような状況は、チームの協力関係やコミュニケーションの質を低下させる可能性があります。 不要な不信感や緊張などを避けるために、「犯人探しをしてはならない」といったグランドルールを設けておくことをおすすめします。
360度評価を導入する際に検討すべき点
360度評価(多面評価)で得られる効果を最大化するためには、設計から運用、現状との接続などにコツが必要です。
効果的な360度評価(多面評価)の設計とは(リンクアンドモチベーションの特徴)
前述のメリットを最大化し、デメリットを最小化するために、リンクアンドモチベーションの360度評価(多面評価)に下記のような特徴があります。
①期待度:各回答項目に対する現状の「満足度」だけではなく、「期待度」も調査し、周囲が何を求めているのか、要望が明確になる設計
②網羅性:役職ごとに求められる役割を網羅的に設計し、「何が求められていて、何が求められていないのか(注力しなくていいのか)」を明示する設計
③具体性:課題となる項目が絞られた上で、すぐにアクションを取ることができる具体的な設問を設計
④偏差値化:数万人の回答を元に、偏差値がわかる設計。人事や上司が状況を把握しやすい。
⑤相対化:結果を突きつけられるだけでは受け止めにくいため、「結果を見たい、改善したい」という思いを引き出す場を設計
効果的な360度評価(多面評価)の運用とは
運用面で注意すべきは下記の点です。
■事務局(人事)
- 活用の目的を明示し、回答者に率直な意見を提出させるために告知する
- サーベイ結果を腹落ちさせるための場の用意する
- 組織・経営の方針や要望を提示する
■回答者:上司(評価者認知)
- 課題を明確にするため、期待度と満足度ともにメリハリをつけた回答をする
- 「基準」を提示するため、現場の意見により過ぎない回答をする
■回答者:メンバー(協働者認知)
- 課題を明確にするため、期待度と満足度ともにメリハリをつけた回答をする
- 関係性を気にするのではなく、相手の成長のために回答をする(気を使った回答をしない)
■参加者(自己認知)
- 全ての意見に迎合せずに、成長や目標達成、目的実現を目指した課題設定をする
- 会社の要望やハイパフォーマーの傾向を踏まえた方向性決定をする
- 個人のビジョンを踏まえ、実現したいプランを策定する
360度評価(多面評価)の評価項目例
360度評価(多面評価)のリンクアンドモチベーションでの項目例を紹介します。特に、管理職向けの項目例は以下の通りです。
参考:日本のミドルマネジャー(中間管理職)の特徴に関する研究結果
■日本のミドルマネジャーの強みである項目
(上司回答版)
- 目の前の目標を達成するために尽力すること
- 自部署の役割や目標を意識した行動をとること
(部下回答版)
- 部下が問題に直面した時に、サポートすること
- 気軽に相談できるオープンでフランクな対応をとること
■日本のミドルマネジャーの弱みである項目
(上司回答版)
- 顧客(関連部署)ニーズの変化や動向を伝えること
- 中長期的な計画を見据えて担当業務を行うこと
(部下回答版)
- 業務に関する評価の基準を明確に示すこと
- 自部署の戦略遂行・目標達成のための具体策を示すこと
マネジメントの360度評価(多面評価)では、上記のような項目を調査しながら、マネジメントの視座・視界は適切に保たれているか、マネジメントが旗を振れば現場は動く信頼関係が築けているのかを測定することができます。
現場の目標を追う力が強すぎると、現場最適が横行し、部署間の連携が阻害される「タコツボ化」や、その部署にとっては良いマネジャーだが全社最適が考えられない「現場の棟梁化」が生じることがあります。
また、テレワークや働き方改革に伴って現場のコミュニケーション不足・マネジメント不足が生じていることもあります。そういった、個別のマネジメント状況を把握することが可能になります。
360度評価(多面評価)のまとめ
これまで、日本企業では年功序列型で、役職が上がってからは明確な節目がなく、成長の機会が少ない状況でした。しかし、現在日本企業は不況の中で強くなることが求められており、一人ひとりの成長が必要です。
また、リモートワークやジョブ型への移行が進む中、相互の成長を支援する仕組みや、ジョブの連動性を高めるための仕組みとして、360度評価(多面評価)に一層注目が集まると予想されます。
上司が部下に、部下が上司に興味を持ち、お互いの成長のために協力し、強い信頼関係で職場をつないでいく。その鍵となるのが、360度評価(多面評価)です。
360度評価(多面評価)の導入事例
360度評価(多面評価)の導入事例をご紹介します。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、パワハラによって社員が自殺する事件が起きたのをきっかけに、再発防止策の一環として360度評価を導入しました。トヨタ自動車の従業員は単独で約7万人、連結で約36万人に上り、課長級以上では約1万人の管理職がいます。この約1万人を対象に360度評価を導入することで、上司や部下、関係部署の社員、場合によっては社外も含め十数人から評価を聞き、仕事上の能力に限らず「人間力」を重視した評価基準に改めました。対象者の強み・弱みに関する周囲の声を集め、本人にフィードバックすることで、自らの行動を振り返り、改善へとつなげる機会にしています。360度評価の結果から「管理職としての適性がない」と判断されれば、昇格が見合わされたり、管理職から外されたりすることもあります。
※参考:労務問題の再発防止に向けた取り組みについて | コーポレート | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/35407637.html
マツダ
マツダでは、一人ひとりの社員が最大限の力を発揮できるよう、個々の成長と活躍を支援し、最適な仕事や環境を提供する人事制度「とびうお」を運用しています。「とびうお」の一環として導入されているのが「コンピテンシー評価」です。同社のコンピテンシー評価は、年1回、事務系・技術系の社員を対象に「仕事への取り組み行動」を評価するものです。仕事をするうえで大切にすべき価値観である「Mazda Way 7つの考え方」に基づいて、社員に期待される仕事への取り組み行動(コンピテンシー評価項目)に対して、自分自身、および上司、部下、同僚、関係先から見た客観的評価(360度評価)をおこないます。360度評価の結果は、キャリアミーティングにおいて上司から本人にフィードバックされ、成長目標や今後取り組むべき課題について話し合います。また、全社における人材の適正配置の参考情報としても活用されています。
▼コンピテンシー評価に関する記事はこちら
コンピテンシー評価とは?導入メリット・デメリットや必要性、導入の手順について解説
※参考:個人を活かした働き方の選択|マツダ株式会社
https://www.mazda.com/ja/careers/newgraduate/system/
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマは2003年より人事評価の制度改革に着手し、「実績」「能力」「360度評価」という3つの基準を用いて評価制度を運用しています。一般社員は、①上司、②同僚、③部下・関連部署の9名ほどから、幹部社員は①上司、②同僚・関連部署、③部下の3方で、所属部署や等級によっては数十名から評価を受けます。社長を含む役員クラスも対象となり、直属の部下から評価を受けています。評価項目は4カテゴリ(幹部社員は業務力、実力、指導力、人間力/一般社員は基本的行動、能力、人間力、実績)・全12項目から構成され、各6段階の評価になっています。同社の360度評価は、社員から「周囲からどう評価されているのかの気づきになる」「自分の強み・弱みを謙虚に受け止められる」など肯定的な声があがっているようです。
※参考:評価制度 | 人 | 取り組み事例 | アイリスグループのサステナビリティ | 企業情報 | アイリスオーヤマ
https://www.irisohyama.co.jp/company/sdgs/activity/human-resources/personnel-evaluation-system/
360度評価(多面評価)のQ&A
Q:360度評価を導入する際の注意点は?
360度評価とは、上司、部下、同僚など、対象となる社員の周りにいる複数の人が評価をおこなう制度です。従来の人事評価制度は上司が部下を評価するのが当たり前でしたが、360度評価は「部下から上司」「同僚から同僚」「他部署から」というように評価の方向が多面的になっているところに特徴があります。このような特徴ゆえに起こりうるのが、フリーコメント欄に誹謗中傷や悪口などが記入されることです。360度評価の目的は対象者に気づきを与えることなので、制度趣旨の理解を促すとともに、フリーコメントの例文・テンプレートを用意するなどの対策も必要です。
Q:管理職を対象とした360度評価の項目例は?
管理職を対象とした360度評価の項目は、マネジメントの在り方を中心にするのが良いでしょう。たとえば、リーダーシップであれば「中長期的なビジョンをメンバーと共有しているか」、組織運営であれば「組織内の連携強化を図るためにコミュニケーションの場を設けているか」、メンバーの育成であれば「部下に役割や期待することを伝えるとともに、適切な支援をおこなっているか」といった項目が考えられます。
Q:一般社員を対象とした360度評価の項目例は?
一般社員を対象とした評価の項目は、スキルやマインドにフォーカスするのが良いでしょう。たとえば、主体性であれば「上司からの指示を待つのではなく、自分で考えて行動しているか」、協調性であれば「周囲のメンバーとコミュニケーションを図り、率先して支援・協力をしているか」、業務遂行力であれば「課題解決のために最善のプロセス・方法を選択し、最後まで遂行しているか」といった項目が考えられます。