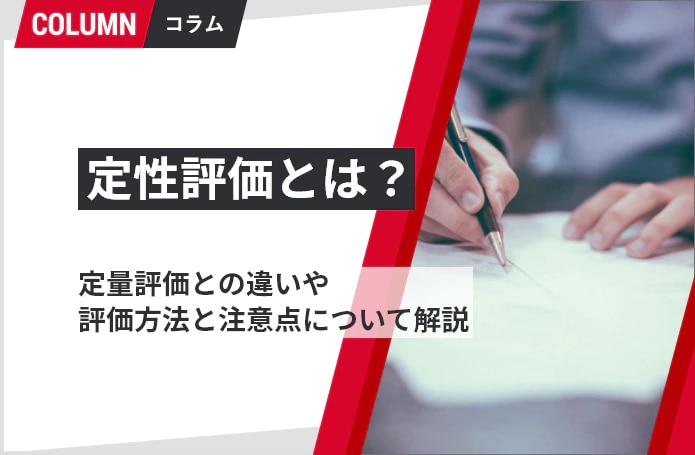
定性評価とは?定量評価との違いや評価方法をわかりやすく解説
人事制度を運用するに当たり、評価は必ず実施されます。その中でも定性評価とは何なのか。定性評価は明確な評価基準が設けられていないことがほとんどです。では、どのような基準で、何に留意して定性評価をするべきか。
この記事では定性評価の概要から方法や注意点などを解説します。適切な人事評価を行う際の参考になれば幸いです。
目次[非表示]
- 1.定性評価とは?
- 2.定量評価との違い
- 3.定性評価の方法
- 4.定性評価のメリット・デメリット
- 5.人事の定性評価で使われる項目
- 6.人事における定性評価の具体例
- 7.定性評価を導入する際の注意点
- 8.記事まとめ
- 9.よくある質問
定性評価とは?
定性評価とは、数値化できない事象に対して評価を下すことです。具体的には、社員のモチベーションや思考、判断力などを評価する際に活用されます。
定性評価は明確な基準を設けにくい一方で、適切に実施することで、社員の業務に対するモチベーションの向上やチームの活性化につながります。一般的には、売上額や販売量などの数値の結果に基づいて行う定量評価と組み合わせて活用される評価方法です。
定性評価は、事務職や保育士、看護師などの職種でよく用いられます。これらの職種では、明確な成果として数値化できるものがありませんが、定性評価を活用することで公正な評価を実現することができます。
定量評価との違い

定量評価とは、定性評価とは真逆の意味を有しており、「数値などの明確な実績や成果で表せる対象を評価すること」です。したがって、定性評価に比べて明確な基準や方針が設けられているので評価しやすく、評価への納得感も醸成しやすいことが特徴です。
人事制度では、定性評価と定量評価を組み合わせて、成果も成長も追求する仕組みを創ることが重要になります。今は成果が残せなくても、この先の未来で成果を残すための成長も応援できる組織創りを意識していきましょう。
定性評価と定量評価の使い方
定性評価と定量評価は、人事評価において重要な役割を果たします。定性評価は、数値で表すことができないものに対する評価、またその評価方法のことです。たとえば、性質や耐性、方針、プロセス、姿勢、気持ち・考え・心構えなど、目に見えないものや形になっていないものを評価する場合、定性評価が用いられます。一方、定量評価は、数値の増減によって達成度を評価するため、目に見えて分かりやすく、具体性があるので評価される側も納得しやすいです。
どちらか一方の手法だけで評価しようとすると、うまく測れない要素が出てしまうことがあります。公正な評価をするには、できる限り両者を組み合わせて総合的に評価することが必要です。例えば、「勤務態度が良くなった」という定性評価だけでは曖昧なので、「遅刻・早退・欠勤が一度もなかった」という定量評価と合わせて総合的に評価する、という具合です。両者を組み合わせて評価することで、精度の高い公正な評価が可能になります。
定性評価の方法
定性評価のための目標設定
定性評価を行う際に必要なものが目標になります。組織として、また個人として、目指す姿に近づくために「何に」「どれだけ」コミットするのか、具体的な行動ベースで、評価者とメンバー間ですり合わせをする必要があります。
リンクアンドモチベーションでは定量目標を「パフォーマンス目標」と定義し、定性目標は「ストレッチ目標」と定義しています。
定性目標である「ストレッチ目標」は少し背伸びすることで成長に繋がる目標として、具体的な行動ベースの目標にし、やったか・やらなかったのかが明確に評価できる目標を設定しています。
定性評価の基準・点数
定性評価をするためには評価者の中に「どのような行動や姿勢を体現していれば、どのような評価点になるのか」という基準がなければ評価できません。したがって、評価者はメンバーごとにあらかじめ「絶対評価の基準」を定めることが求められます。
「絶対評価の基準」は個々人が設定した定性目標に対してどれだけコミットするのかという個人がやったかやらなかったかを評価する基準になります。
さらに個人だけではなく、組織全体から見た時にどうだったかを考えるために評価点を調整する必要があります。評価点を調整する際は下記の2段階の相対比較を実施します。
①グループ間の評価基準を相対的にすり合わせる
部署内のグループ、あるいは部署間の基準を事前にすり合わせておくことで組織全体での納得感を醸成する必要があります。
②同グレード(階層)のメンバー同士を個別に比較して調整する
組織内で同等の能力レベルであると定されているメンバーを横並びで見て、評価点を調整することでメンバー間の納得感を醸成する必要があります。
定性評価のメリット・デメリット
【メリット】
<数字に出ない仕事への評価>
定性評価は実際の成績以外にも評価する要素があるため、数字として成果がでにくい従業員に対しても正しく評価することができます。
<従業員のモチベーションアップ>
自身の役割期待がブレイクダウンされた指針が具体的に示されるため、社員にとって「わかりやすく」「道に迷わない」メリットがあります。これこそが、従業員のモチベーションアップに重要な観点です。
【デメリット】
<評価の難しさ>
定性評価は定量評価のように明確な数値的基準を設定することができないため、どうしても評価者の主観が反映される可能性があります。また定量評価であれば結果だけを見れば評価できるというのに対し、定性評価は過程も見なければならないため評価者への負担が大きくなります。
<評価に対する不満>
評価される側が評価に対して納得できないという可能性もあります。定性評価の項目は人によってはあまり重視していないことであったり、自身が予想していた評価と食い違うということが発生することがあるためです。
人事の定性評価で使われる項目
定性評価として用いられる項目は、企業によって様々です。しかし、1から新しいものを考えなければならないわけではなく、ある程度他社で多く活用されている項目を利用しながら、自社に合う使い方を模索することが大切です。
代表的な定性評価の項目として、以下のようなものが挙げられます。
①スピード性
②創意工夫
③知識
④協調性
⑤規律性
⑥積極性
⑦責任
■①スピード性
業務を迅速に遂行する能力。時間を有効に使い、期限内に成果を出すことが求められます。
■②創意工夫
独自のアイデアや工夫を持ち込む能力。新しい解決策やアプローチを提案し、革新的な成果を生むことが期待されます。
■③知識
業務に必要な知識を持ち、適切に活用する能力。専門的な知識を持ち、業務の効率化や品質向上に貢献することが求められます。
■④協調性
チームでの協力や協調を重視する態度。他のメンバーとの協力を通じて、チーム全体の成果を向上させることが期待されます。
■⑤規律性
ルールや規則を守り、自己管理する能力。組織の規範を遵守し、安定した業務遂行をすることが求められます。
■⑥積極性
自発的に行動し、主体的に業務を進める態度。自らの意志で業務に取り組み、成果を上げることが期待されます。
■⑦責任
自分の業務に対する責任を持ち、結果を出す態度。自らの業務に対して責任を持ち、成果を出すことが求められます。
人事における定性評価の具体例
人事における定性評価には、様々なケースがあります。ここでは、定性評価の具体例について、いくつかご紹介します。具体例の中から自社で活用できる要素を抽出しつつ、効果的な定性評価の運用方法をご検討ください。
■ 売上アップのバックグラウンドを評価
ある企業の営業部門で、売上が20%上昇したとします。営業部門が20%アップした背景には、被評価者の努力があると考えられます。ここでは、評価の方法として定性評価を用いた場合の例を考えてみましょう。例えば、以下のように定性項目を評価することができます。
顧客へのフォローを欠かさなかった
顧客へのフォローアップは、ビジネスにおいて非常に重要です。営業部門が顧客との信頼関係を築くために、継続的なフォローアップ活動を行い、顧客に対して献身的であることを示すことができます。また、定期的なフォローアップにより、顧客のニーズや要望を理解し、より良いサービスを提供することができます。そのため、顧客へのフォローを欠かさなかったことが、高く評価されるのは当然のことです。
パンフレットや資料を改善し、商品の強みを分かりやすくした
営業部門が商品の魅力を伝えるために、パンフレットや資料を改善したことが高く評価されます。この取り組みが、顧客へのアプローチにつながり、売り上げアップに寄与しました。
この取り組みには、以下のような工程が含まれます。まず、営業部門は商品の強みを分析し、それをパンフレットや資料に反映させるために、専門家のアドバイスを受けました。次に、デザイン部門と協力して、より分かりやすく、魅力的なパンフレットを作成しました。また、商品の使用方法や特長など、より詳細な情報を提供するために、資料も改善しました。
このように、商品の魅力を伝えるためのパンフレットや資料の改善は、営業部門にとって非常に重要な取り組みであり、その成果は顧客へのアプローチや売り上げアップにつながります。
営業部門が抱える間接部門業務を効率化した
営業部門が間接部門業務を効率化したことは、組織にとって大きな成果となりました。この取り組みによって、営業部門は本来の営業活動に集中することができるようになりました。また、業務の効率化によって、社員たちはストレスを軽減でき、モチベーションが高まりました。さらに、顧客満足度も向上し、長期的なビジネスパートナーシップを築くことができました。
営業部門が間接部門業務を効率化したことが高く評価されます。この取り組みが、営業部門が本来の営業活動に集中できるようになったことで、売り上げアップにつながったと考えられます。
これらの項目は、数値で示すことができないが、営業部門の売り上げアップに寄与した要因として評価されるべきです。また、これらの取り組みは、顧客との信頼関係を築き、商品の魅力を伝えるために必要な取り組みであり、営業部門の成功に必要なものです。
■ 新卒入社の従業員の評価
新卒入社の従業員の評価を行う際にも、定性評価を活用することができます。新卒入社の従業員は、多くの場合売上や利益に直接繋がるスキルや経験を有していないことが多く、定量的な評価のみを行うことが難しいでしょう。
そのため、定性評価をもとにして評価を行うことで、より仕事に対する姿勢や取り組み方といった面にスポットを当てることができます。
評価する内容の例としては、以下のような項目が挙げられます。
自主的に勉強会を開催した
新卒入社の従業員が自らの成長のために努力をしていることを示すものであり、評価されるべきです。自主的に勉強会を開催することは、自らの知識を向上させるための取り組みであり、業務に対する意識の高さを示すものです。
チームが円滑に回るように進んで雑用を引き受けた
チームの一員としての協調性を示すものであり、評価されるべきです。新卒入社の従業員が進んで雑用を引き受けることは、チームの一員としての責任感を示すものであり、チームの円滑な運営に寄与するものです。
自らの意見を積極的に発信した
新卒入社の従業員が自らの意見を積極的に発信することは、自己主張の力を示すものであり、評価されるべきです。自らの意見を発信することは、自分の考えを他者に伝えるためのコミュニケーション能力を示すものであり、チーム内での意見交換を促進するものです。
他者の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを行った
新卒入社の従業員が他者の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを行うことは、他者とのコミュニケーション能力を示すものであり、評価されるべきです。他者の意見に耳を傾けることは、他者の意見を尊重する姿勢を示すものであり、チーム内での意見交換を促進するものです。
業務に対する熱意を持ち続けた
新卒入社の従業員が業務に対する熱意を持ち続けることは、モチベーションの高さを示すものであり、評価されるべきです。業務に対する熱意を持ち続けることは、自らの成長のために努力をしていることを示すものであり、業務の品質向上に寄与するものです。
これらの具体例は、定性評価を用いて評価を下す際の参考としてください。定性評価は、数値で示すことができないが、評価されるべき要因を評価するために重要な手法です。
定性評価を導入する際の注意点
上記のデメリットにもありますように、定性評価では評価者の主観が反映される可能性があります。
主観に基づいた評価ではなく、客観的な視点から事実に基づいて評価できるようにしましょう。まずは自分自身の思考のクセを把握することが重要になります。
ここではそれぞれのメリットを具体的にお伝えします。
■好き嫌いや人間性で評価しない
相手の全体の印象など「人」に対して評価するのではなく、設定した目標に向かって取り組んだ客観的事実に対して評価する必要があります。
このとき陥りやすい状態をハロー効果と呼んでいます。ハロー効果とはある対象を評価するときに目立ちやすい特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる事象のことを言います。
■直近の出来事に惑わされない
評価期間の期末に素晴らしい業績をあげた、逆に失敗したからと言って、それ以前の出来事や取り組みを軽視せず評価期間全体から評価する必要があります。
■これが良ければあれも良いはずを避ける
知識が豊富ならば判断力もある、というように論理的に関係があると思われることを全て同じ評価で勝手に連動させず、項目ごとに1つ1つ評価する必要があります。
■自分を基準にしない
自分の得意なことに関しては厳しく、不得意なことは甘く評価したり、評価者自身の能力や価値観を基準に評価せず、各等級の評価項目を基準に評価する必要があります。
■メリハリのない評価を避ける
全ての評価項目について、格差のない評価を付けるのではなく、長期的な育成の観点も踏まえ、十分な情報収集に基づいて、評価を通じたステップアップに向けた「期待」や「課題」をメッセージする必要があります。
■自分自身のクセを知る
全ての従業員に対して甘い評価または辛い評価を付ける等、自分自身の評価のクセを知ったうえで、客観的に評価する必要があります。
記事まとめ
いかがだったでしょうか。
定性評価とは個人の成果だけではなく、成長を促す重要な評価制度になります。また、個人だけに留まらず、組織の風土改革や離職率の低減にも繋がります。
定性評価を人事制度に組み込むことによって、個人と組織に大きな変化が生まれることを願っています。
よくある質問
定性評価とは?
定性評価とは「数値などの明確な実績や成果では表せない対象を評価すること」です。業務への向き合い方(スタンス)や処理能力や行動(スキル)などは、数値やデータでは表すことができません。また今は実績や成果に結びつかないとしても、これからの成長に繋がる姿勢や行動も評価要素に当たる場合があります。このような対象を評価する際に用いられるのが定性評価です。
定性評価のメリット・デメリット
定性評価のメリット・デメリットとして以下のようなものがあります。
■メリット①:数字に出ない仕事への評価
定性評価は実際の成績以外にも評価する要素があるため、数字として成果がでにくい従業員に対しても正しく評価することができます。
■メリット②:従業員のモチベーションアップ
自身の役割期待がブレイクダウンされた指針が具体的に示されるため、社員にとって「わかりやすく」「道に迷わない」メリットがあります。これこそが、従業員のモチベーションアップに重要な観点です。
■デメリット①:評価の難しさ
定性評価は定量評価のように明確な数値的基準を設定することができないため、どうしても評価者の主観が反映される可能性があります。
■デメリット②:評価に対する不満
評価される側が評価に対して納得できないという可能性もあります。






