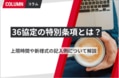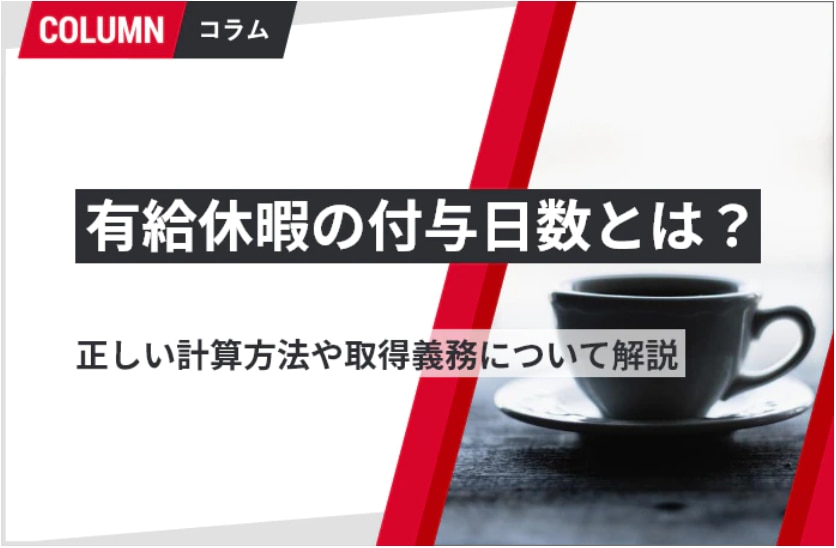
有給休暇の付与日数とは?正しい計算方法や取得義務について解説!
御社は従業員に正しく有給休暇を付与できていますか? 有給の付与・取得に関するルールは複雑で、正社員とアルバイト・パートでは計算方法も異なります。また、2019年の法改正によって従業員の有給休暇消化が義務化されました。
あらためて、年次有給休暇の仕組みや管理方法について確認しておきましょう。
目次[非表示]
有給休暇の発生要件
企業は業種や規模にかかわらず、また正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たしたすべての従業員に対して年次有給休暇を付与する必要があります。
■条件1.出勤率が8割以上で6か月間継続勤務している
年次有給休暇は、従業員が雇用開始日から6ヶ月間勤務を継続し、その期間中の出勤率が80%以上の場合に付与されます。この休暇を取得することで、従業員は仕事に復帰する際には、より生産的でエネルギッシュな状態で戻ってくることができます。企業は、従業員の健康や幸福に対して配慮することで、従業員のモチベーションや生産性を向上させることができます。
出勤率
出勤率は以下の式で計算されます。
出勤率=出勤日/全労働日(その期間の総歴日数から所定休日や不可抗力による休業日等を除いた日数)×100
出勤日の定義
出勤日として計算に含める日は以下の通りです。
業務上の理由による負傷や疾病で療養のために休業した期間
育児・介護休業期間
産前産後の女性が休業した期間
年次有給休暇取得日
具体例
例えば、4月1日に入社し、有給休暇の付与日(基準日)が10月1日の場合、この半年間の日数は183日で、所定休日数が52日あるとします。この場合、全労働日は131日になります。したがって、131×0.8=104.8となるため、105日以上出勤していれば、有給休暇の取得条件である「出勤率80%以上」を満たしていることになります。
■条件2.有給休暇の増え方
年次有給休暇に関する労働基準法の規定
労働基準法に基づくと、フルタイム労働者は、入社後の半年経過時点で10日以上の有給休暇を受け取ることができます。これは、労働者が適切な休息を取り、仕事とプライベートのバランスを保つことができるようにするためです。
さらに、労働者は、入社から数年後には、年次有給休暇の日数を増やすことができます。これは、労働者が長期的なキャリアプランを持ち、長期的な雇用を希望することを促すためです。たとえば、入社から6年半後には、年間20日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数が増えるにつれて、さらに多くの休暇日数を受け取ることができます。
しかしながら、20日は、有給休暇を年間で取得できる最大日数です。つまり、社員は、1年に最大で20日間の有給休暇を取得できますが、年によって付与される日数は異なります。この制限は、企業が生産性を維持し、業務の中断を最小限に抑えることを可能にするためです。
したがって、労働者は、十分な休息を取るために、有給休暇を上手に活用する必要があります。また、企業は、従業員が適切な休息を取ることができるよう、有給休暇の取得を促進することが重要です。
具体例
例として、従業員が初めて有給休暇を受け取る際に10日を受け取った場合、2回目の付与では11日、3回目では12日と、1日ずつ増加します。4回目以降は、2日ずつ増加し、14日、16日、18日と続きます。そして、入社から6年半後には、20日が付与されます。
出勤日の定義
出勤日の計算には、実際の労働日だけでなく、以下の日も含まれます。
・業務上の理由での休業日(例:業務中の怪我や病気)
・育児や介護の休業日
・産前産後の休業日
・有給休暇取得日
具体例
4月1日に入社し、10月1日が有給休暇の基準日とすると、この半年間は183日となります。所定休日が52日の場合、全労働日は131日です。出勤率が8割を満たすためには、この131日の80%、すなわち105日以上出勤する必要があります。
■有給休暇がもらえる時季とは?
原則として、従業員は自らの希望に応じて有給休暇の取得日を指定することができます。これが、有給休暇の「時季指定権」です。ただし、会社側は、従業員が指定された日に有給休暇を取得することで事業の正常な運営に支障が生じるときは、従業員に取得日の変更を求めることが認められています。これが、有給休暇の「時季変更権」です。会社が時季変更権を行使しない場合、従業員は自ら指定した日に有給休暇を取得することができます(労働基準法第39条5項)。
なお、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかは、一般的に、当該従業員の所属する事業場を基準として、事業の規模・内容、当該従業員の担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行など諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきであるとされています。
有給休暇の付与日数の計算方法は?
年次有給休暇の付与日数は法律で定められています。フルタイムの従業員と所定労働日数が少ないパート・アルバイトでは、有給休暇の付与日数が異なるため注意が必要です。
■正社員・契約社員の有給休暇は継続勤務年数をもとに計算
正社員や契約社員の有給休暇は、継続勤務年数に基づいて付与日数が計算されます。具体的には、労働基準法により、入社後半年経過時に10日以上の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに日数が増加します。例として、初回付与が10日、2回目は11日、3回目は12日と増加し、4回目以降は2日ずつ増加します。最大で1年に20日が上限となります。
また、「フルタイムの従業員」の定義は、週の所定労働時間が30時間以上、または所定労働日数が週5日以上、もしくは年間の所定労働日数が217日以上となります。
例えば、以下のように継続勤務年数に応じた有給休暇付与日数が表されます。
継続勤務年数 |
半年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
有給付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
■パート・アルバイトに対する有給休暇付与日数
正社員と同様に、パート・アルバイトについても有給休暇を付与する必要があります。パート・アルバイトや派遣社員などの従業員は、正社員と比べて少ない日数の勤務をする場合がありますが、その労働日数で有給付与日数が決まります。
所定労働日数が週5日の場合(年217日以上):
週の所定労働時間が30時間未満でも、週5日勤務の場合、正社員と同じ日数の有給休暇が付与。
所定労働日数が週4日の場合(年169~216日):
雇入れ日から半年後に7日の有給休暇が付与。3年6ヶ月勤務後には年10日の有給休暇が付与。
所定労働日数が週3日の場合(年121~168日):
雇入れ日から6ヶ月後に5日の有給休暇が付与。5年6ヶ月勤務後には10日の有給休暇が付与。
所定労働日数が週2日の場合(年73~120日):
初回の基準日で3日の有給休暇が付与。その後、年ごとに4日・4日・5日・6日・6日・7日分が付与。
所定労働日数が週1日の場合(年48~72日):
雇入れから6ヶ月後に1日の有給休暇が付与。
表にまとめると、以下のようになります。
|
|
週の
所定労働日数 |
1年間の
所定労働日数 |
継続勤務年数 |
||||||
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
|||
|
有給休暇
付与日数
|
5日 |
217日以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
|
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
|
1日 |
48~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
|
有給休暇の管理を効率化する方法
企業は従業員の年次有給休暇を適切に管理する必要があり、有給休暇を付与する従業員がいる企業には「年次有給休暇管理簿」の作成が義務付けられています。 ですが、従業員の数が多ければ多いほど有給休暇の管理は煩雑になり、手間や時間がかかります。担当者の負担を軽減するためには、Excelやシステムを使って有給管理をするのがおすすめです。
■Excelによる有給管理
従業員数がそれほど多くない会社であれば、Excelでも効率的な有給管理が可能です。Excelなら使い慣れている従業員も多く、誰でも抵抗なく扱えます。また、無料でダウンロードできるテンプレートも多数あるので、すぐにでも運用を始められます。
■システムによる有給管理
近年では、有給管理機能のある勤怠管理システムや労務管理システムが数多く登場していますし、有給管理に特化したシステムも増えています。このような業務システムを導入すれば、有給管理の負担を軽減できるだけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながるでしょう。
有給休暇を使用した場合の計算方法
有給休暇を使用した場合、賃金はどのように計算されるのでしょうか。前提となる考え方について、確認しておきましょう。
■通常出勤と同じ
有給休暇を取得した場合、賃金の計算が必要です。賃金の計算方法はいくつかありますが、どの方法を使用するかは事前に就業規則に記載する必要があります。従業員ごとやタイミングによって賃金の計算方法を変更することはできません。
例えば、月例給が30万円の従業員が有給休暇を1日使用した場合、1ヶ月分の給与を支払う方法があります。つまり、有給休暇を取得した日は、通常出勤と同じ扱いをすることになるということです。
このように、有給休暇の取得には一定の条件があり、それに基づいて賃金の計算が行われます。従業員が有給休暇を取得した場合、賃金の計算は必須ですので、適切な計算方法を選択し、就業規則に記載することが重要です。
■平均賃金を用いて金額を計算する
次に、平均賃金を用いて金額を計算する方法をご紹介します。
有給休暇を使用した場合の賃金計算方法として、平均賃金を用いて金額を計算する方法があります。この方法では、直近3ヶ月の賃金総額をベースとして計算します。
具体的な計算方法は以下の通りです。
・直近3ヶ月間の賃金総額を求めます。
・その賃金総額を直近3ヶ月間の勤務日数で割ります。これにより、1日あたりの平均賃金が求められます。
・有給休暇を取得した日数に1日あたりの平均賃金を掛けます。これにより、有給休暇を取得した場合の賃金が求められます。
例えば、直近3ヶ月間の賃金総額が300,000円、勤務日数が60日、有給休暇を取得した日数が5日の場合、1日あたりの平均賃金は300,000円 ÷ 60日 = 5,000円です。したがって、有給休暇を取得した場合の賃金は5,000円 × 5日 = 25,000円となります。
この計算方法は、有給休暇を取得した場合の賃金を公平に計算するためのものです。従業員が有給休暇を取得しても、その期間の賃金が適切に支払われることが保証されます。
■標準報酬月額を用いて金額を計算する
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の算定に使われている等級ごとの報酬です。この標準報酬月額を用いて、有給休暇を使用した場合の賃金を計算することができます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
・対象となる従業員の標準報酬月額を算出します。
・その金額を所定労働日数で割ります。これにより、標準報酬月額に基づく1日あたりの賃金が求められます。
・有給休暇を取得した日数に1日あたりの賃金を掛けます。これにより、有給休暇を取得した場合の賃金が求められます。
例えば、標準報酬月額が220,000円、1ヶ月の勤務日数が20日の従業員が有給休暇を取得した場合、1日あたりの賃金は220,000円 ÷ 20日 = 11,000円です。有給休暇を5日間取得した場合、55,000円の賃金を支払う必要があります。
ただし、標準報酬月額を計算方法として用いる場合には、労使協定を結ばなければいけないことに注意が必要です。
年5日の有給休暇取得の義務化
■ポテンシャル採用とは
2019年3月までは、従業員に年次有給休暇を取得(消化)させることについて、企業側に義務はありませんでした。しかし、労働基準法の改正により、2019年4月以降は「年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に年5日の有給休暇を取得させること」が義務付けられました。
フルタイムで働く従業員の場合、有給付与日数は「10日」からスタートするのでこの義務の対象になります。パート・アルバイトなど、所定労働日数が少ない従業員も勤続期間によっては10日以上の有給休暇が付与されるため、その場合は対象になります。
また、管理監督者や有期雇用労働者もこの義務の対象になります。管理監督者に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:管理監督者とは?定義と役割、管理職との違いについて解説!
年5日の有給休暇取得が義務化された背景としては、有給休暇取得率の低さがあります。かつての日本企業は、年次有給休暇が付与されてもそれを使いにくい(取得しにくい)という企業風土があり、それが過重労働を招く原因にもなっていました。昨今は、適切に有給休暇を取得させることによって、従業員の健康維持やワークライフバランスの実現をサポートしようという企業が増えています。実際に、令和2年の年次有給休暇の平均取得率は56.6%で、昭和59年以来過去最高の数値になっています。
有給休暇付与日数を算出する際の注意点
有給休暇の付与日数を間違えるなどのミスがあると、従業員の信頼を失うだけでなく、罰則が科せられるリスクもあります。ミスが起こらないよう、有給休暇付与日数を算出する際のルールや計算方法は正確に理解しておきましょう。
■年次有給休暇は繰越しができる
従業員は付与された有給休暇を付与された年にすべて取得する必要はなく、翌年度へ繰越しすることができます。ただし、繰越しができるのは1年間だけで、それ以降の繰越しはできません。
■育児や介護などによる休業期間は出勤したものとみなされる
年次有給休暇の発生要件である「出勤率が8割以上かどうか」を判断する際、もし従業員が以下の理由によって休業している期間があっても、その期間は出勤したものとしてみなさなければいけません。
・業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間
・育児休業、介護休業をした期間
・産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
従業員がこれらの理由で休んだ日があっても、出勤日数からマイナスする必要はないということです。
■従業員によって異なる基準日を統一することができる
年次有給休暇を付与するタイミングは、基本的にその従業員の入社日を基準日として決定します。しかし、中途入社の従業員が多い会社などは従業員ごとに入社日が異なるため、「誰がいつまでに有給を5日取得しなければならないのか?」など、有給休暇の管理が煩雑になります。
これを避けるために、基準日を月初や年度始めに統一することが認められています。このように年次有給休暇を付与するタイミングを統一することを「斉一的取扱い」と言います。斉一的取扱いをすることで有給管理の負担が軽減され、ミスの防止につながります。
・基準日を年始や年度始めに統一する場合
人員規模の大きな会社や新卒一括採用をしている会社などは、基準日を年始(1月1日)や年度始め(4月1日)に統一することができます。
・基準日を月初などに統一する場合
中途採用をおこなっている会社や比較的小規模な会社などは、基準日を月初などに統一することができます。たとえば、月の途中に入社した従業員がいても、同じ月に入社した従業員全員の基準日を月初に統一することで管理の負担が軽減されます。
なお、基準日を変更する場合は必ず前倒しにする必要があり、後ろ倒しにすることはできません。また、会社の判断だけで基準日を変更することはできません。あらかじめ労使間で合意したうえで就業規則を変更し、全従業員へ周知する必要があります。
■出勤率が8割に満たなかった年も勤続期間に含まれる
上述のとおり、雇入れの日から6ヶ月継続して雇われており、全労働日の8割以上を出勤している従業員には年次有給休暇を付与する必要があります。逆に言えば、入社後6ヶ月以上勤続していても、出勤率が8割未満の従業員に対しては年次有給休暇を付与する必要はありません。
ただし、8割出勤の条件を満たさなかった年も勤続年数には含まれます。たとえば、入社1年の従業員で、全労働日に対する出勤率が8割に満たなかった場合、2年目に有給休暇を付与する必要はありません。出勤率が8割以上なら、2年目には「11日」の有給休暇が付与されるはずでしたが、この場合、2年目の有給休暇は「ゼロ」になります。
しかし、2年目の出勤率が8割以上であれば、3年目に「12日」の有給休暇が付与されます。2年目の有給休暇がゼロだったからと言って、3年目の有給休暇の付与日数が2年目の「11日」になるわけではなく、あくまでも3年目の付与日数である「12日」を付与するということです。
有給休暇の消滅時効と買い取り
有給休暇の有効期間は労働基準法115条によって「上限2年」と定められており、2年を経過すると時効によって消滅します。上述のとおり、前年度に取得しなかった有給休暇は翌年度に繰越すことができますが、さらにもう1年繰越すことはできません。
とはいえ、従業員によっては期間内にすべての有給休暇を取得するのが難しいケースもあるかもしれません。その場合、会社が余った有給休暇を買い取ることはできるのでしょうか? 原則として、有給休暇の買い取りはできませんが、以下の3つのケースでは例外的に買い取りが認められています。
・有効期限を過ぎた場合
2年の有効期限を過ぎてしまった有給休暇がある場合、会社はそれを買い取ることができます。ただし、買い取るかどうかは会社の任意であり、従業員から有給休暇の買い取りを求められても、会社はそれを拒否することができます。
・退職日までに取得しきれない場合
従業員が退職することが決まっており、退職日までに有給休暇を取得しきれない場合は、従業員と協議のうえ同意を得れば買い取ることができます。
・法定の日数より多い有給休暇を付与している場合
会社独自の福利厚生などで、法定の日数より多く有給休暇を付与している場合は、法定の日数より多い分の有給休暇を買い取ることができます。たとえば、法定の有給休暇が10日の従業員に15日の有給休暇を付与していたら、5日分は買い取ることができます。
労働基準法の有給休暇に関する要件に違反した時の罰則
会社が有給休暇について定めた労働基準法第39条に違反した場合、罰則が科されることがあります。2つのケースで罰則についてご説明します。
■ケース① 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合
すべての事業者は、年次有給休暇が10日以上発生した従業員に、年5日の年次有給休暇を取得させなければいけません。この規定に違反した事業者は、対象となる従業員一人につき30万円以下の罰金が科されることがあります。違反した従業員一人につき1罪として取り扱われ、違反した従業員が10人いた場合、事業者は最大300万円の罰金を支払わなければなりません。ただ、罰則対象は事業者のみで、従業員への罰則はありません。
また、違反していることが発覚した場合、労働基準監督署からの指導が入り、改善がみられない場合は、さらなる罰則が課されます。そのため、事業者は従業員の有給休暇取得状況を把握しておき、取得するように働きかけましょう。
なお、夏休みや年末年始など特別休暇の一部を労働日に変えて有給を取得させるなど、実態を伴わない抜け道のような対応策は脱法行為として捉えられるリスクが高まるため、注意が必要です。
■ケース② 所定の年次有給休暇を与えなかった場合
6ヶ月以上継続勤務し、その間の出勤率が8割以上の従業員には、労働期間や労働時間に応じた年次有給休暇を付与しなければいけません。この規定に違反した事業者は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることがあります。この場合も、対象となる従業員一人につき1罪として取り扱われるため、対象となる従業員が100人いれば罰金は最大で3,000万円になります。
まとめ
年次有給休暇の管理は非常に煩雑です。出勤率の算出や付与するタイミング、年5日の取得義務も含めた取得の状況など、管理すべき項目は多岐にわたり、従業員数が多くなるほど業務負荷も大きくなります。
最適な体制を整えて、ミスなく効率的に従業員の有給管理をおこなっていきましょう。適切に有給を取得することで心身の健康を保ち、企業と従業員のエンゲージメントを向上させていきましょう。
有給休暇に関するよくある質問
有給休暇とは?
有給休暇は、労働者が通常の給与を受け取りながら休暇を取得できる権利です。この休暇は、労働者が自身の健康やリフレッシュのために利用できます。有給休暇は、労働基準法に基づいて付与されるもので、労働者の権利として保護されています。
有給休暇が付与される条件は?
日本の労働基準法によれば、有給休暇は以下の条件を満たす労働者に付与されます。
・6か月以上の勤務が必要。
・その期間中に80%以上の出勤が必要。
有給休暇の日数は、勤務日数に応じて増加します。例えば、6か月間の勤務で10日間、1年6か月で11日間、2年6か月で14日間、3年6か月で16日間、4年6か月で18日間、5年6か月で20日間の有給休暇が付与されます。
有給休暇はパートやアルバイトにも付与される?
有給休暇はパートタイムやアルバイトの労働者にも付与されます。ただし、付与される日数は、労働時間や勤務日数に応じて異なる場合があります。パートタイムやアルバイトの労働者も、上記の条件(6か月以上の勤務、80%以上の出勤)を満たす場合、有給休暇を受け取ることができます。