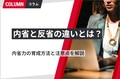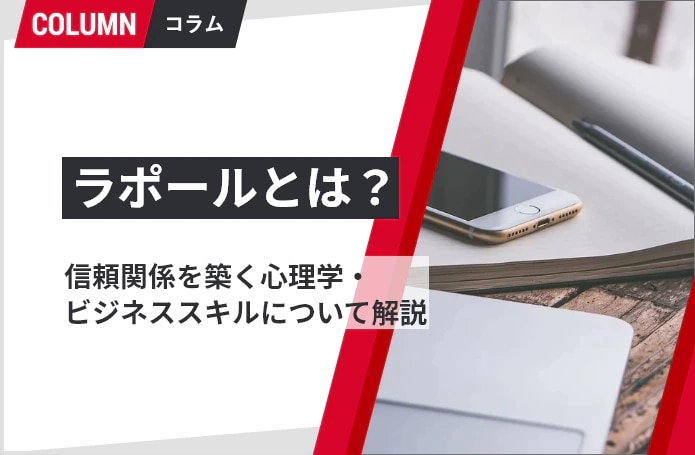
ラポールとは?信頼関係を築く心理学・ビジネススキルについて解説
ラポールというワードをあまり聞きなれない方も多いと思います。
ラポールとは心理学の世界で使われている用語で、信頼関係という意味があります。ラポールが形成されていると、お互いに本音を打ち明けられるようになり、コミュニケーションの精度が高まります。
本記事では、コミュニケーションをとる上での”安心のインフラ”としてのラポールの効果や、ラポールを形成する上でのポイントを紹介します。
目次[非表示]

ラポールの意味とは?関係性を表す心理学用語
ラポールはフランス語の「RAPPORT」が語源と言われており、「橋を架ける」という意味から、お互いに心が通じ合い、安心して相手を受け入れることを表します。
ラポールという言葉は、元はオーストリアの精神科医が、自身とクライアントの間の関係を表現するために用いた臨床心理学の用語でした。
その後、セラピストとクライアントで信頼関係をもとに、安心して振る舞える状態、感情の交流を行える関係が成立している状態を表す際に、このラポールという用語が使われ流ようになりました。
このラポールですが、上述のように臨床心理学の領域にとどまらず、ビジネスの場面における対人関係においても使われることがあります。
部下や後輩に向けたマネジメントの際にも、取引先との商談の際にも、ひいては家族関係においても、相手とのラポールを築き、信頼の土台の上でコミュニケーションを取らなければ、本当の悩みを打ち明けてもらえない、課題を打ち明けてもらえない、といったことが起こります。
ビジネスとはコミュニケーション活動だと言うことができると思います。コミュニケーションの質を高めるためには、その土台となるラポールを築くことがポイントになります。
本記事では、主にビジネスシーンにおけるラポールについて紹介します。
ラポールの築き方・テクニック
では、相手とラポールを築くポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、4つのポイントを紹介します。
■テクニック①:ミラーリング
ミラーリングとは、読んで字のごとく、鏡に写したかのように相手の動作をまねるという方法です。
特に、ノンバーバル面をまねることで、相手とのラポールが形成しやすくなります。
具体的には、下記のようなポイントを意識することが重要です。
声:声の大きさや、話すスピード
顔:表情や目線
体:姿勢やジェスチャーなど
また、自動的に相手と行動が似てくるという副次的な効果も伝えられています。長年連れ添った夫婦の行動が、徐々に似てくるのもこのミラーリングの効果の表れだと言われています。
相手と自然と行動の癖が似ることで親近感が生まれ、ラポールを形成・強化することができると言われています。コミュニケーションの際に、相手と同じタイミングで同じ表情で笑う、同じタイミングで同じ動きするなどといった工夫を意図的に取り入れることがポイントです。
■テクニック②:ペーシング
上記のミラーリングに良く似たテクニックとして、ページングがあります。ミラーリングが相手の仕草や行動そのものを鏡のように真似ることに対して、ページングは相手に合わせてコミュニケーションを取るというテクニックです。
神経言語プログラミング(NLP)という学問で提唱されているコミュニケーションスキルが元になっています。ポイントはミラーリングの時と同様に「声」「顔」「体」の3点です。相手の話すスピードに合わせる、話題のトーンにあった相槌を行うなどといったことを意識することがポイントです。
具体的には、相手が適切な言葉を選びながらゆっくり話している時には、同じようなペースでゆっくり話す、
相手があえて小さな声で内輪だけで済ませたそうな内容を話している時には、同じくらいの声のボリュームで話すといった工夫をすることで、相手に自分を理解してもらっているという感覚を与え、ラポールを形成しやすくなります。
一方で、過剰にページングを行うと、相手にわざとらしく感じられることがあるため注意が必要です。
■テクニック③:キャリブレーション
他にも、ラポールを築くテクニックとしてキャリブレーションがあります。
一般的に、キャリブレーションとは「調整する」といった意味で使われることが多いですが、心理学では、相手の言葉以外の情報を観察し、相手の状態を認識するためのスキルといった意味で使われます。
要は、相手を観察し、バーバル情報以外の部分から相手の心理状態を気づく力です。
例えば、喧嘩後のほとぼりが冷めきっていない中、相手が腑に落ちない表情、低いトーンの声で「もう怒ってないから」と言われたとしても、本当に相手の怒りが静まったとは思わないと思います。
相手の心理状態を正しく認識しないまま、コミュニケーションを取ってしまうと、ラポールが崩れてしまうことにつながりかねません。逆に、言葉以外の情報を観察し、コミュニケーションに活かすことで、相手が自分のことを分かってくれているという感覚を醸成することができます。
具体的には、相手が納得しきっていなさそうな表情を読み取って補足説明を行ったり、相手の疲れていそうな表情を読み取って端的に要点を絞って伝えるようにしたりと、キャリブレーションで得た情報を活かしたコミュニケーションがポイントとなります。
■テクニック④:バックトラッキング
もう一つのラポールを形成するテクニックとして、バックトラッキングがあります。
バックトラッキングとは、元々は「情報の塊を戻す」という意味で使われていた言葉ですが、心理学の世界では、「オウム返し」と呼ばれるような、相手のいったことをそのまま返すテクニックとして使われます。
実際に精神科の医療現場などでも、相手の感情を同じ言葉で繰り返すことによって、安心感や信頼関係を構築し、大切にされているという肯定感を醸成するため、このテクニックが使われています。
ポイントは相手の使っている言葉をそのまま使うことです。
具体的には、相手が「悔しかった」という言葉で表現してきたのであれば、「悔しかったんだね」と返すことが重要です。
逆に「悔しかった」という言葉に対して、「無念だったんですね」「心残りだったんですね」「反省しているんですね」などといったように、異なる言葉を使ってしまうと、相手が自分のことを理解してくれていないという感情を抱くリスクもあります。
下手に自分の言葉を使わず、相手の言葉を使うことがポイントとなります。
▼心理的安全性の高い組織をつくるマネジメント4つのポイント 資料はこちら
ラポールを築く時の注意点
ラポールを築くためのテクニックについてご説明しましたが、ただ単にテクニックを用いるだけではラポールを築けないどころか、相手との関係性を悪化させてしまう可能性もあります。ラポールを築こうとする場合は、以下の注意点に配慮するようにしましょう。
相手を否定しない
ラポールを築こうと思ったら、相手を否定してはいけません。相手を否定するような言動や態度をとると共感や信頼が生まれにくくなり、ラポールを形成するのが難しくなります。その場のコミュニケーションが悪化するだけでなく、「この人とはあまり話をしたくない」など、その後のやり取りにも影響が及んできます。相手を否定せず、相手の意見や気持ちに対して理解を示すことがラポールを形成するための重要なポイントです。自分と考えが違う場合でも、まずは相手を理解していることを示し、考えを擦り合わせていく姿勢が大切です。
自然な形でテクニックを用いる
上述したミラーリングやペーシングなどの手法はラポール形成に効果がありますが、過度に用いると相手に不信感を与えてしまうことがあります。たとえば、自分の仕草や言葉をずっと真似されていると気付いた相手は、違和感を覚えるでしょう。また、相手に合わせることを意識しすぎると、相手はわざとらしさを感じるものです。ラポールを形成するためには、自然な形でミラーリングやペーシングなどの手法を用いることが大切です。自然で心地良いコミュニケーションができれば、安心感や信頼感を与えられるでしょう。
相手をよく観察する
相手をよく観察することで、表情や仕草、身振りなどから重要な情報が得られることがあります。たとえば、相手が目をそらしたり不機嫌そうな仕草をしていたりしたら、何か都合の悪いことがあるのかもしれません。このように言葉だけでは伝わらない心理状態を読み取ることができれば、それを踏まえてより適切な対応をすることができるでしょう。また、相手をよく観察することで「あなたに興味があります」「あなたの話に注意を払っています」という姿勢を伝えることもできます。
ラポールを築くことの効果やメリット
ラポールを築くことによる大きなメリットとしては、相手の深層を引き出すことができる点にあります。信頼している親友に対して心の悩みを打ち明けることはあっても、会って間もない人に全てを打ち明けるということは、まずないかと思います。
信頼関係がなければ、要は、ラポールが形成できていなければ、心の悩みを打ち明ける、吐き出すことはできません。逆に、相手が信頼できる人にしか打ち明けない内容を聞き出すことができれば、部下のマネジメントがうまく行ったり、商談をうまく進めたりすることができます。
自分と相手の関係性を踏まえた情報収集を、ジョハリの窓の概念を使いながら説明します。
ジョハリの窓は、アメリカの2人の心理学者が提唱した、対人関係における相互認識を表した考え方です。

開放の窓:自分が認知していて、相手も認知している情報
秘密の窓:自分は認知しているが、相手は認知していない情報
盲点の窓:自分は認識していないが、相手が認識している情報
未知の窓:自分が認識しておらず、相手も認識していない情報
相手とのラポールが形成されていると、相手が自己開示する情報が多くなり、秘密の窓が小さくなります。
この開放の窓を下に広げるためのポイントがラポールの形成です。
▼コミュニケーションスキルに関する記事はこちら
コミュニケーション能力とは?ビジネスにおける重要性や効果的な話し方、能力向上のポイントを解説
ラポール形成のビジネスにおける効果
ビジネスにおいては、社内外のステークホルダーとラポールを形成することが重要です。ラポールを形成することができれば、「コミュニケーションが充実する」「話の説得力が増す」「心理的安全性が高まる」など、様々な効果が期待できます。
コミュニケーションが充実したものになる
ラポールが形成されていれば、お互いがよりオープンな姿勢でコミュニケーションを図ることができます。遠慮や忖度をすることなく、伝えたいことをストレートに話すことができるので、コミュニケーションが生産的・建設的なものになりやすいです。また、ラポールが形成されているとお互いの心理的距離が近くなるので、相手の感情や思考をより正確に読み取ることができます。相手を理解したうえで、より深く充実したコミュニケーションを図ることができるでしょう。
信頼関係が深まる
ラポールを形成することでお互いの信頼関係が深まります。そのため、安心して自分自身を開示できるようになり、相手に自分のことを良く理解してもらえるようになります。相手の価値観や興味を知ることで、より親近感や好感を持つことができるでしょう。部下や同僚、顧客などとラポールを形成することができれば、お互いの気持ちや視点を理解しやすくなり、より良いサポートやより良い取引ができるようになるなど、好循環が生まれるはずです。
話の説得力が増す
誰でも信頼している人の話には真剣に耳を傾け、その話を受け入れようとするものです。ラポールが形成されている関係では、相手の発言に対して受容の姿勢ができているので、話の説得力が増します。さらに、相手の関心や価値観などの情報をもとにアプローチすることで、より相手に響く話をすることができるでしょう。逆に、ラポールが形成されていない関係は、信頼できる人かどうかを探っている状態なので、話の説得力も不十分なものになります。
ビジネスの成果につながる
たとえば、上司や部下、同僚との間でラポールが形成されていれば、お互いが目標に向かって連携・協同しやすくなり、チームビルディングが強化されます。コミュニケーションがスムーズになり、情報共有も円滑に進むため、課題解決や生産性向上などビジネスの成果につながりやすくなるでしょう。また、顧客との間にラポールが築かれると顧客満足度が向上し、長期的な関係性の土台ができます。加えて、顧客のニーズをより正確に把握できるようになるので、商品やサービスの改善を図りやすくなります。その結果、成約率やリピート率の向上へとつながるでしょう。
心理的安全性が高まる
ラポールが形成されている状態ではお互いが相手を尊重しているので、お互いに安心して発言することができます。「これを言ったら、相手にどう思われるだろう・・・」などと心配することなく、自分の意見や考え方を率直に話すことができる環境、いわゆる「心理的安全性」が高い環境が生まれます。心理的安全性が高い職場では、メンバーが自由に意見を出し合い、異なる視点から様々なアイデアを積極的に共有するので、より創造的な問題解決やイノベーションが生まれやすくなると言われています。
ラポールの構築により、仕事が成功した事例
ここでは、ラポールの構築による成功事例を、事業面と組織面の2つの側面から紹介します。
■顧客の価値観を理解した提案を行うことができる
冒頭でビジネスはコミュニケーション活動だと記載しました。
顧客とのコミュニケーションを通じて、支持や共感を得ることがビジネスでは求められます。
ビジネスにおけるコミュニケーションの要素は「受信」「発信」が求められ、ゴールとして「感化」が必要になります。
受信:相手の意図を汲み取る
発信:相手に伝えたい内容が伝わる
感化:相手の行動変革を促す
相手が求めているものを見極め(受信)、求めているものに合った解決方法を提案し(発信)、相手の購買行動を促す(感化)ことが必要です。
ビジネスにおけるコミュニケーションのステップや要素を紹介しましたが、コミュニケーションの起点は「受信」にあります。
相手が求めているものを適切に把握できなければ、その後の発信が的を得ないものになり、感化まで至りません。
この受信の質を高めるためのポイントがラポールの構築です。
相手からより多くの情報を引き出すためには、相手とのラポールの構築が不可欠です。この人になら悩みを打ち明けたい、この人にならお願いしたいという関係性を築けると、自然と感化までのステップに持っていきやすくなります。
ビジネスにおいては、友人関係、家族関係と異なり、短期間でラポールを築くことが求められます。
そのためには、上述の4つのテクニックを有効活用することが求められます。
特に、ページングとバックトラッキングの手法が有効です。
相手によって心地よい話のスピードやトーンは異なります。相手のスピードやトーンに合わせて話をすることで、打ち合わせの短い時間を通じてラポールを築きやすくなります。
そして、相手の使っている言葉をそのまま使うことも大きなポイントです。企業ごとに文化が異なるため、企業ごとに使い慣れている言葉、馴染みやすい言葉は異なります。
そして、企業ごとに無意識的に使っている言葉、好んで使う言葉には、その企業の価値観が表れます。
相手の使っている言葉をそのまま使うことで、相手に「自分たちと考え方が似ているな。うちに合った会社なのかもしれないな」という感覚を醸成することができます。その結果、相手の共感を創造しやすくなり、取引に繋がる可能性を高めることができます。
■心理的安全性を高め、若手が成長しやすい環境を作ることができる
職場内、先輩後輩間でラポールを築くことで、相談しやすい関係性が生まれ、若手の成長を促進することができるようになります。
このことは、心理的安全性という言葉で表現されることが多いのですが、組織内でメンバーが発言を恥じたり、拒絶したり、罰を与えるようなことをしないという確信を得れているかどうかがポイントです。
心理的安全性を築くことで、特に若手は「分からないことを聞いてもいい」「間違っても良い」「チャレンジしてもいい」「他の人と違ってもいい」という感覚を持つことができるようになります。
このように、特に若手の成長のために、土台となる心理的安全性は非常に重要な要素なのですが、COVID-19の影響で、従業員に対してリモート勤務を実施する企業が増え、この心理的安全性の構築に困難を感じる企業が増えてきています。
リモート勤務下で、心理的安全性の構築の障壁として、下記のようなものが上げられます。
- Web会議が主体となり、相手の感情が読み取りにくい
- チャットやメールの連絡が主となり、相手に冷たく伝わりやすい
- 気軽な雑談の機会が減り、安心感を得にくい
- 相手の業務中の様子が見えず、疑心暗鬼になりやすい
このような障壁が存在することを加味して、職場内でラポールを築くことが求められます。手法としては、定期的に何でも相談できる1on1を設ける、任意参加のランチタイム用Web会議システムを用意する、コミュニケーションの頻度を増やすなどの取り組みを行う企業が増えてきています。
これらの手法を用いて職場内でラポールを構築することで、分からないことがあった時に、何でも聞ける心理的安全性が生まれ、若手が成長しやすい環境を整えることができます。
また、ラポールを構築しておくことで、部下や後輩の悩みをいち早く察知し、離職を防ぐ可能性を高めることもできます。
▼【1on1】に関する記事はこちら
1on1とは?効果的な進め方やテーマ例、失敗原因まで紹介
ラポールを築き、信頼の土台の上でマネジメントをするなら、リンクアンドモチベーション
ここまでラポールの定義や効果、築き方等について説明いたしました。
弊社のストレッチクラウドでは、ラポールを築き、信頼の土台の上でマネジメントができる人材を育てるために、まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。
その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。 結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。
ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。また、ラポールに関連するマネジメントコミュニケーション研修 も下記にてご紹介しますので、ご興味あればぜひご確認ください。
▼参考: ストレッチクラウドの詳細はこちら
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service
▼参考:マネジメントコミュニケーション研修
https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/management/lincoln_action
記事まとめ
ラポールの構築はビジネスの土台となるコミュニケーションを適切に行う上で非常に重要です。
ラポールを構築することで、顧客に対しても、自組織に対しても適切な受信を行うことができるようになり、事業成果・組織成果を高めることができます。
▼コミュニケーション能力に関する記事はコチラ
ビジネスにおけるコミュニケーション能力の重要性と能力向上のポイントを解説
ラポールに関するよくある質問
ラポールとは?
ラポールはフランス語の「RAPPORT」が語源と言われており、「橋を架ける」という意味から、お互いに心が通じ合い、安心して相手を受け入れることを表します。ビジネスは企業と顧客間のコミュニケーションの中で成り立ちますが、そのコミュニケーションの質を高めるためには、土台となるラポールを築くことがポイントになります。
ラポールを築くメリットや効果は?
信頼関係がなければ、要は、ラポールが形成できていなければ、心の悩みを打ち明けたり、吐き出したりすることはできません。逆に、相手が信頼できる人にしか打ち明けない内容を聞き出すことができれば、部下のマネジメントがうまく行ったり、商談をうまく進めたりすることができます。