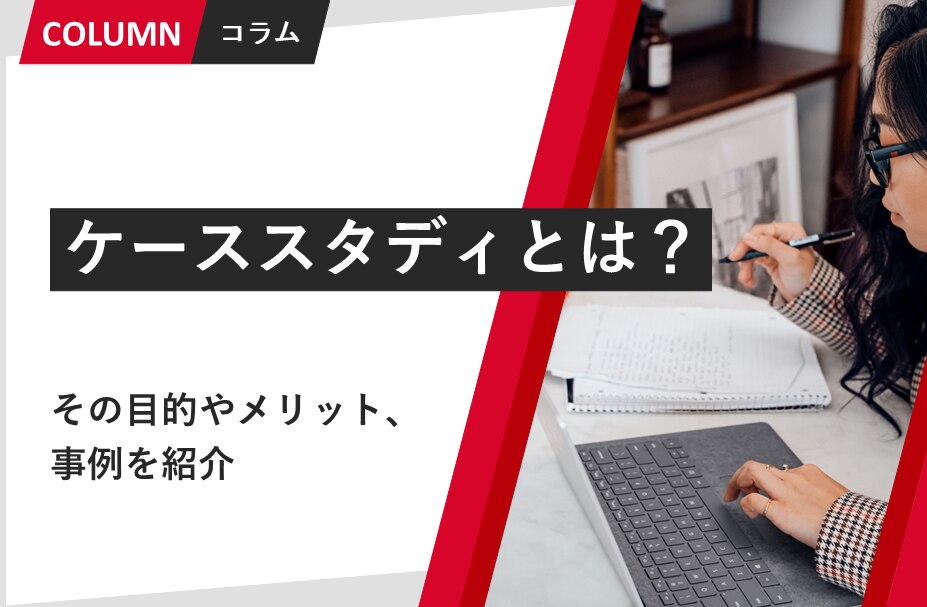
ケーススタディとは?用語の意味やメリット、適切なやり方を簡単に解説
ケーススタディとは、日本語で「事例研究」のことで、実際に起きた事例を分析して、その背後にある法則や傾向を究明していく研究手法のことを言います。また、事例をベースにした教育手法もケーススタディ(ケースメソッド)と言われ、実際に起きた事例を疑似体験して、そこから問題を発見したり最適な解決策を導き出したりしていきます。今回は、ケーススタディの意味や目的、メリットや進め方などについて解説していきます。
目次[非表示]
ケーススタディの意味とは?
ケーススタディ(case study)とは、日本語で「事例研究」のことで、実際に起きた事例を分析して、その背後にある法則や傾向を究明していく研究手法のことを言います。辞書では、ケーススタディを以下のように定義しています。
現実に起こった具体的事例を分析、検討し、その積み重ねによって帰納的に一般的な原理、法則を引き出す研究法。事例研究。個別調査。
※参考:精選版 日本国語大辞典|小学館
ある具体的な事例について、それを詳しく調べ、分析・研究して、その背後にある原理や法則性などを究明し、一般的な法則・理論を発見しようとする方法。事例研究法。
※参考:デジタル大辞泉|小学館
また、事例をベースにした教育手法もケーススタディ(ケースメソッド)と言われます。実際に起きた事例を疑似体験して、そこから問題を発見したり最適な解決策を導き出したりしていきます。ケーススタディをおこなうことで、理論の学習だけでは得られない実践的な問題解決スキルや意思決定力を養うことができます。
ケーススタディの実施目的
ケーススタディの目的は様々ですが、ビジネスにおいては問題解決力や意思決定力を向上させるためにおこなわれるのが一般的です。ビジネスでは、困難な状況に直面するシーンが多々あります。そんなとき、課題を解決したり、的確な意思決定をしたりすることができるようになるには、何よりも場数を踏むことが重要です。しかしながら、一人の人間が身をもって経験できることには限界があります。
ケーススタディをおこなうことで、数多くの多様な事例から知見・ノウハウを得ることができます。環境変化がますます激しくなる昨今、日々生じる様々な問題を予測・発見・解決していくために、ケーススタディは欠かせない取り組みだと言えるでしょう。
ビジネスにおけるケーススタディとは?
ケーススタディは、企業において研修プログラムに取り入れられることが増えています。特に、リーダー研修や管理職研修ではケーススタディがおこなわれることが少なくありません。
ビジネスにおけるケーススタディでは、実際にあった事例を疑似体験し、様々な考察をすることで問題解決やリスク回避、アイデア創出などの力を磨いていきます。ケーススタディを重ねることで、理論だけでは対応するのが難しい局面においても的確な意思決定ができるようになります。
教育におけるケーススタディとは?
教育の分野においては、事例研究を重視した教育手法としてケーススタディが取り入れられており、ビジネススクールでもケーススタディを活用した様々なプログラムが設けられています。
教育手法としてのケーススタディでは、実際に起こった事例の当事者になったつもりで考察をしたうえで、参加者同士がディスカッションするのが一般的です。「もし自分が当事者だったら、その状況下でどのような意思決定・行動をするのか?」ということを考え、参加者同士の議論を通して学びや気付きを得ていきます。
看護におけるケーススタディとは?
ケーススタディは、医療や看護の分野においても取り入れられており、医師や看護師が集まって事例紹介や事例検討をおこなうのが一般的です。医療や看護の現場においては瞬時に的確な判断をすることが求められるため、ケーススタディをどれだけ重ねているかによって対応力に差が生まれてきます。
看護領域のケーススタディでは、「看護研究」よりも簡易的であるため、「プレ看護研究」や「事例研究」などとも呼ばれます。一つの事例をもとに自らアセスメントや診断を行うことにより、問題解決能力やロジカルシンキングの訓練に役立てることができます。
また、看護におけるケーススタディには大きく二つの手法があります。
①ヒストリカルスタディ
通常のケーススタディとして多く登場するのがヒストリカル・スタディです。ヒストリカルスタディとは、事例の一連の過程を取り上げて個別的な問題解決を行うために研究する方式です。主に、患者1人を対象とした個別的な問題解決を行う場合に用いられます。
②インシデントスタディ
インシデント・スタディとは、一つの患者の一連のケースを理解するヒストリカルスタディとは違い、一つの「症例」を複数の角度から掘り下げるケーススタディを指します。患者1人だけではなく、複数の患者を対象とし、比較検討する場合に用いられるため、看護研究に近い方式と言えます。
ケーススタディを実施するメリット
ケーススタディをおこなうことによる主なメリットについてご説明します。
効率的に多くの事例を疑似体験できる
ビジネスにおける問題解決力や意思決定力を高めるためには、理論を知るだけでなく実践を積むことが重要です。しかし、上述したように一人の人間が経験できることには限界があります。
ケーススタディをおこなえば、自分が経験したことのない事例も疑似体験でき、効率的にビジネススキルの向上を図ることができます。不測の事態に直面した場合でも、「今回の状況はあの事例に似ている」という関連付けができれば、より的確な対応ができるはずです。
問題解決力が向上する
ケーススタディでは、過去の事例をベースに「自分が同じ状況だったらどうするか?」を考えることによって、より効果的な解決策を見いだしていきます。ケーススタディを重ねることで個々の問題解決力が高まり、結果として組織・チームとしても問題解決力の向上が期待できます。また、予期せぬ問題に直面したときにも慌てることなく、冷静かつ粘り強く解決に取り組めるようになります。
分析力・実践力が身に付く
座学で学んだ理論や知識は、頭では理解できていても、実践に移すとなると難しいケースがあります。一方、ケーススタディでは具体的な事例を分析し、最適解を導き出していくことを通して分析力や実践力を養うことができます。これらの能力はビジネスパーソンにとって重要な能力であり、特にマネジメント層にとっては不可欠な能力です。そのため、マネジメント層の育成にケーススタディが用いられることも少なくありません。
新しいアイデアを創出できる
ケーススタディで過去の成功事例を題材にした場合でも、必ずしもその事例における手法が正解であるとは限りません。ケーススタディのプロセスにおいて、「これ以外の方法はないのか?」「もっと良い解決策はないのか?」と追求することで、今までは思いつかなかったような解決策や新しいアイデアを発見できることもあります。また、ディスカッションをして他の人の意見を聞いたり、他の人の考え方と組み合わせたりすることで、相乗的なアイデアを創出できることもあります。
リスクを回避できる
ケーススタディでは、失敗事例も疑似体験することができます。事故や判断ミス、業績悪化やクレームなどの失敗が起きた原因を分析することで、リスクを発見したり回避したりする力を強化できます。過去の失敗事例を知らなければ、リスクをリスクとして捉えることすらできない可能性もありますが、ケーススタディによって失敗事例が頭に入っていれば、小さなリスクの芽も摘み取ることができるでしょう。
業務効率化につながる
ビジネスは意思決定の連続であり、特に管理職の仕事は意思決定のウエイトが大きくなります。管理職が意思決定に悩んだり迷ったりしていると、メンバーが動けなくなるなど、業務効率の低下につながることがあります。また、ビジネスのスピード感が失われ、ときに機会損失を招いてしまうこともあるでしょう。ケーススタディによって過去の事例から法則や傾向を見いだすことができていれば、試行錯誤することなくスピーディーに意思決定をすることができます。一つひとつの意思決定のスピードが上がれば、組織全体の業務効率も上がりますし、機会損失を防ぐことにもつながります。
メンタルを強化できる
ケーススタディを実施するメリットは多岐にわたりますが、特にトラブルが生じた際の適応力の向上やメンタルの強化に重要な役割を果たします。この方法論は、実際の事例や問題を詳細に分析し、様々な状況での対処法を学ぶことを可能にします。
トラブルが生じた場合、ケーススタディを通じて得た知識や経験は、迅速かつ効果的な対応を導くのに役立ちます。これにより、不測の事態に対しても柔軟に対応できる適応力が身に付きます。また、実際の事例を扱うことで、理論だけでは得られない現実感を伴った学習が行えるため、メンタルの強化にも寄与します。
対面する問題が現実的であるほど、解決に向けてのモチベーションや自信が高まり、精神的な耐性が育まれるのです。
ケーススタディの課題
ケーススタディは有効な研究・教育手法ですが、以下のような点には注意する必要があります。
唯一無二の正解が得られるわけではない
ケーススタディは、過去の事例を分析することで法則や原理を抽出したり、過去の事例を考察することでより良い解決策やアイデアを導き出したりする手法です。しかし、今後同じようなケースに遭遇した場合に、「過去の事例でうまくいった方法をそのまま当てはめられるわけではない」ということは認識しておきましょう。ケーススタディは唯一無二の正解が得られるものではなく、過去のケーススタディと同じやり方でうまくいくとは限りません。
また、ケーススタディでは理解を容易にするために事例をシンプルにすることがあります。しかし、実際に遭遇する事例は複雑で入り組んでいることが多いため、ケーススタディで学んだことだけを頼りにしていると、誤った判断をしてしまう可能性もあります。
古い事例は今後に活かせないおそれがある
ケーススタディでは基本的に過去の事例を分析・研究していきますが、題材にする事例が古いものだと良質な学びが得られないどころか、逆に誤った意思決定をする原因になってしまうこともあります。
VUCAの時代と言われる昨今は環境変化が激しく、昨日まで正解だったことが、今日には不正解になっているような例も各所で見られます。また、ITを中心としたテクノロジーが急速に進歩しているため、古い事例から得られた知見・ノウハウが通用しないというケースも少なくありません。ケーススタディで題材にする事例は定期的に見直し、バージョンアップを図る必要があるでしょう。
ケーススタディのやり方・進め方
ケーススタディは以下の手順で進めていくのが一般的です。
STEP① 題材にする事例を選ぶ
ケーススタディで題材にする事例を選定します。事例は、自社における過去の事例を選ぶこともありますし、公開されている他社の事例を取り上げることもあります。
STEP② テーマを決める
事例を選んだら、ケーススタディのテーマを決定します。たとえば、「売上アップの施策を考える」「課題解決策を提示する」「新サービスのアイデアを提案する」といったテーマです。
STEP③ 事例を理解して結論を導く
ケーススタディの事例を読み込んで、その背景や問題点などを把握します。必要な情報が不足している場合などは、管理者・主催者への質問を認める場合もあります。事例から得た情報を整理し、自分の考えをまとめ、テーマに対する結論を導き出していきます。なお、ケーススタディの参加者に事前に事例を共有して準備をしてきてもらうことで、当日の進行をスムーズにすることができます。
STEP④ ディスカッションをする
参加者がグループに分かれてディスカッションをおこないます。各参加者が自分の結論を共有し、意見交換をしながら、他の参加者との意見の違いを知ったり、自分にはなかった考えに触れたりすることで、結論をブラッシュアップしていきます。
STEP⑤ 発表する
グループとしての結論が固まったら、グループごとに発表をおこないます。グループごとの結論を比較・検討しますが、正解探しをしたり、良し悪しを決めたりすることが目的ではありません。ここまでのプロセスのなかで気付きを得たり、新しい視点や発想に触れたりすることで問題解決力や意思決定力を高めることがケーススタディの本質です。
ケーススタディ事例の作り方・集め方
ケーススタディの事例を自社で収集・作成して、管理職研修などで活用する企業も少なくありません。事例を作成する際の大まかな手順についてご説明します。
ケーススタディ事例の作成計画を立てる
ケーススタディをおこなう目的によって、どんな事例を作成すべきかが変わってきます。そのため、まずはケーススタディの目的を明確にして、作成すべき事例の要件を決定します。また、作成すべき事例の数や期限、担当者なども決定します。担当者は、直近で問題解決に当たったメンバーやプロジェクトで成果を創出したメンバーをアサインするのが良いでしょう。
ケーススタディ事例を作成する
担当者は、自ら手がけた事案をケーススタディ用の事例としてアウトプットします。このとき、作成方法を担当者に任せるとアプトプットがバラバラになり、ケーススタディに活用しにくくなってしまいます。そうならないよう、事前にフォーマットを定めておくことが重要です。
なお、ケーススタディの事例は「このような場面に遭遇したら、あなたならどうする?」と問いかけるものです。この問いに対する解答も用意すべきですが、それが正解である必要はありません。そもそもケーススタディに正解はないという前提で、一つの解答例を用意すれば十分です。
ケーススタディ事例をカテゴリ分けする
各担当者からケーススタディの事例が集まったら、それぞれの事例をカテゴリ分けします。カテゴリは自社がケーススタディをおこなううえで管理・活用しやすいもので構いません。製造業であれば「品質管理」「業務効率化」「コスト削減」など、サービス業であれば「顧客満足」「クレーム対応」などがカテゴリの一例になるでしょう。
ケーススタディに関連する用語
ケーススタディの関連語として「ケースメソッド」「ケーススタディ試験」「ケーススタディ面接」について解説します。
ケースメソッド
ケースメソッドとは、実際に起きた事例を題材にして、事例の分析から問題解決までを疑似体験する教育手法です。過去の事例を疑似体験し、ディスカッションしながら最善策を導き出すことで実践的な問題解決力を養っていきます。ケースメソッドはもともと、米国のハーバード・ビジネス・スクールで生み出された手法であり、日本でも管理者研修やリーダー研修などに取り入れられています。
ケーススタディ試験
ケーススタディ試験とは、ケーススタディを取り入れた試験のことを言います。管理職登用試験にケーススタディを取り入れている企業も少なくありません。ケーススタディをおこなうことで、与えられた事例から問題を発見する力や分析する力、課題を解決へと導く力、困難な状況を打開する力など、リーダーとしての資質を総合的に把握することができます。
ケーススタディ面接
ケーススタディ面接とは、ケーススタディを取り入れた面接のことで、「ケース面接」とも呼ばれます。応募者の論理的思考力やコミュニケーション能力、困難に対処するポテンシャルや限られた時間内で問題を処理する能力などを見極めるのに適していると言われます。コンサルティング会社などでは、ケーススタディ面接を取り入れている会社も多々あります。
ケーススタディ面接は、面接官が提示した事例に対して応募者が解決策を提示するパターンが一般的です。グループ面接の形式でおこなわれることも多く、数人の応募者同士でディスカッションをしてもらい、一人ひとりの応募者の考え方や発言などを評価していきます。
まとめ
自分一人の経験から学べることには限界がありますが、ケーススタディを活用すれば、自分が経験したことのない事例も疑似体験でき、効率的にビジネススキルの向上を図ることができます。組織単位で過去の事例をケーススタディとしてまとめていけば、知見・ノウハウを資産化でき、全社員の学びを促進することができるはずです。
また学びを最大化するために、リンクアンドモチベーションでは、ケーススタディを実施する際、「グループダイナミクス」を設計に組み込んでいます。
「グループダイナミクス」とは、認知心理学に端を発する、集団力学を活用した個々人の気づきや変化を促進する技術です。代表的な例としては下記のようなものがあげられます。
①鏡映自己:鏡に映った自分に気づくことで、「○○なつもりの自分」と「鏡に映った自分」のギャップから、気づきを促進する。
②自己表出:自分の心情・価値観などを他者に対して開示することによって、前向きな姿勢の醸成を促す。
③参画意識:集団活動において自分が一定の役割を果たしているという感覚を持つこと。傍観者に終わらないよう、主体性や当事者意識を引き出すことで、態度変容を促す。
④利他実感:自分が他者に対して役立っているという実感、他者に対する貢献感を持つこと。他者にアドバイスを行うことにより、自分自身にも言い聞かせる効果を狙うことで、態度変容を促進する。
⑤自己投影:他者の中に自分の姿を見る機会をつくり、自分に似た他者を客観視すること(もしくは感情移入すること)で、自分自身の思考や行動の軌道修正を促す。
⑥他者理解:集団の他者の心情などを理解する機会をつくり、深い他者理解を通じて気づきを与え、態度変容を促す。
⑦普遍性:自分の悩みや弱みが、他者の中にもある一般的なものだと気づく機会をつくり、「なーんだ、自分だけじゃなかったんだ!」という気付きによって、心の重荷から解放され、前向きな思考・行動を促す。
⑧競争意識:集団において他者に負けまいとする意識を持つことにより、前向きな姿勢を醸成し、態度変容を促す。
ケーススタディは与えられた答えを覚える学習ではなく、「この場合、自分ならこうする」と考えることで、問題に直面したときの「引き出し」を増やすような取り組みです。ぜひケーススタディに加え集団力学を加味した場の設計をすることで、臨機応変な判断力・対応力を持った従業員を育てていきましょう。
ケーススタディに関するよくある質問
Q:ケーススタディを使った例文は?
ケーススタディを使った例文としては、以下のようなものが挙げられます。
- ケーススタディでは、イレギュラーな事例を取り上げることも重要だ。
- 今日のクレーム対応はケーススタディにして、他部署にも共有すべきだ。
- 管理職研修だけでなく、新人研修にもケーススタディを取り入れたほうが良い。
Q:ケーススタディとケースメソッドの違いは?
ケーススタディもケースメソッドも、過去の事例から学びを得るという点では共通していますが、厳密に言えば異なる手法です。
ケーススタディ(事例研究)は、実際に起きた事例を分析して、その背後にある法則や傾向を究明していく研究手法のことを言います。一方、ケースメソッドは、実際に起きた事例を題材にして、分析から解決までを疑似体験する教育手法です。両者にはこのような違いがありますが、明確に使い分けられているとは言えず、ケーススタディをケースメソッドと言ったり、ケースメソッドをケーススタディと言ったりすることも少なくありません。
Q:ケーススタディの事例はどのように集める?
ケーススタディの事例は自社の事業活動のなかから集めることも大切ですが、自社の事例ばかりだと偏りが生まれたり、カテゴリが限定されてしまったりします。そのため、外部から収集することも重要です。Web上で公開されているケーススタディもありますし、論文や書籍、新聞などから探すこともできます。また、ビジネススクールやセミナーでもケーススタディの事例を集めることができます。





